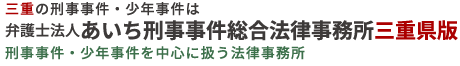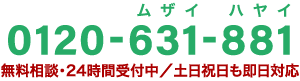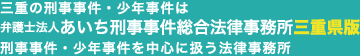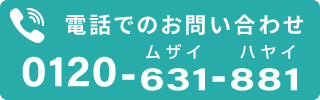Author Archive
【解決事例】インターネット掲示板での誹謗中傷 名誉棄損罪で被害届
【解決事例】インターネット掲示板での誹謗中傷 名誉棄損罪で被害届
【解決事例】インターネット掲示板での誹謗中傷によって、名誉棄損罪で被害届を出された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
伊賀市内に住んでいるAさん(45歳、会社員)は、サイクリングを趣味にしており、同じ趣味を持つ者同士でサークルを作り週末等に活動していました。
そんな中Aさんは、サークルの運営を巡ってある人物をとトラブルになってしまいました。
Aさんは、この人物がサークル内で、自分の悪口を言いふらしていると思い込み、仕返ししてやるつもりで、インターネット掲示板に「伊賀市●●(実際の住所)に住んでいる●●(実名)は、援助交際をしている。」「●●(実名)は不倫の常習者」等と複数回書き込みをしたのです。
その結果Aさんは、この人物に名誉棄損罪で三重県伊賀警察署に被害届を出され、警察の取調べを受けることになりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
名誉棄損罪
名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を傷付ける犯罪です。
ここでいう「公然と」とは、不特定多数の人の目に晒される事です。
Aさんのようにインターネット掲示板への書き込みは、その掲示板の閲覧者に知れることとなるので、名誉棄損罪でいうところの「公然と」に該当するでしょう。
続いて「事実を摘示する」という部分についてですが、名誉棄損罪における「摘示」とは「人の社会的評価を低下させる具体的事実を認識可能な状態にする」事です。
「援助交際をしている。」とか「不倫している。」とい書き込みをすれば、当然ながらその人の社会的評価を低下させることになるので、Aさんの行為が名誉棄損罪に抵触することは間違いないでしょう。
インターネット掲示板での誹謗中傷
インターネット掲示板等での誹謗中傷が大きな社会問題になっています。
インターネットは匿名性が高く、誰が書き込んだか分からない安心感からか、その内容が非常に過激になりがちですが、昨今、こういった書込みに悩まされる方が増えており、警察は取締りを強化しています。
またこういった現状を踏まえて、インターネットでの誹謗中傷被害を抑止するために侮辱罪が厳罰化される見通しです。
厳罰化された場合、これまでの法定刑「拘留または科料」が、「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」となる見通しで、これによって、公訴時効は1年から3年に延びます。
このコラムをご覧の方で、インターネット掲示板での誹謗中傷や、名誉棄損罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。ちなみにこの事件を起こしたAさんは、被害者との示談によって不起訴となっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士の無料法律相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にて受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
【解決事例】桑名市のショッピングモールで盗撮して現行犯逮捕された事件
【解決事例】桑名市のショッピングモールで盗撮して現行犯逮捕された事件
桑名市のショッピングモールで盗撮して現行犯逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは、ある休日、桑名市のショッピングモールで盗撮事件を起こし目撃者に現行犯逮捕されて三重県桑名警察署に連行されました。
Aさんは、エスカレーターにおいて、女性のスカート内をスマートホンで盗撮していました。
警察署で取調べを受けた際に事実を認めていたAさんは、留置されることなく釈放され、その日のうちに帰宅することができました。
そしてその後、被害者との示談が成立したことから不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
桑名市の盗撮事件
三重県の迷惑防止条例では「正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること。」を禁止しています。
Aさんのように、ショッピングモールのエスカレータにおいて、女性のスカート内を盗撮すればこの条例に違反することになります。
罰則規定は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」ですので、起訴されて有罪が確定すればこの罰則規定内で刑事罰が科せられることになります。
盗撮事件の量刑
被害者との示談がなかった場合、盗撮事件で有罪が確定すると、初犯であればほとんどの場合で略式起訴の罰金刑となるでしょう。
そして2回目の場合は、起訴されて執行猶予付きの判決となり、3回目では実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。
しかしこの量刑はあくまでも目安であって、初犯でも余罪が多数ある場合は、起訴されて正式裁判にかけられる可能性がありますし、短期間の間に再犯を犯した場合は、より厳しい処分となるでしょう。
余罪や、盗撮事件の前科前歴の有無によって大きく左右されるので、刑事処分に不安のある方は一度弁護士に相談することをお勧めします。
示談できれば不起訴の可能性が高くなる
盗撮事件は、被害者との示談ができれば不起訴となる可能性が高くなります。
不起訴になれば、規定されているような刑事罰が科せられることはなく、前科も付きません。
しかし不起訴になったからといって全てがなくなるわけではありません。
警察署で採取された指紋や、撮影された被疑者写真等の記録は、警察組織の中で半永久的に保管され、今後の犯罪捜査に活用されるので注意が必要です。
このコラムをご覧の方で、桑名市の盗撮事件でお困りの方、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
【GWも休まず営業】連休中に事件、事故に巻き込まれたら・・・
【GWも休まず営業】連休中に事件、事故に巻き込まれたら・・・
三重県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、連休中(GW)も休まず営業しています。
本日は、連休中に事件、事故に巻き込まれた場合の対処について解説します。
昨日から連休が始まり、中にはこの連休を利用して旅行に出かけている方もいるかと思います。
ここ三重県にも、この連休中は多くの方にお越しいただいていますが、そんな楽しい連休、多くの人が出歩いているため、予期せぬ事故や事件に巻き込まれることもあります。
そこで本日は、この連休中にご家族が、事件、事故に巻き込まれて警察沙汰になってしまった場合の対処について解説します。
連休中によくある事件
お酒を呑んでのトラブル
旅先でついお酒の量が増えてしまってトラブルになるというのはよく聞く話です。
当事者同士の話し合いで解決できればいいですが、時には殴り合いに発展し、警察沙汰になってしまうこともあります。
旅行先で傷害事件を起こすと、身元確認が取りにくいために、逮捕されてしまうリスクが高くなるので注意が必要です。
交通事故
電車等の公共交通機関を利用する方なら問題ありませんが、車を運転して移動される方であれば、みなさん交通事故に巻き込まれる可能性があるので運転には十分注意してください。
連休中は、普段運転なされない方がハンドルを握っていたり、開放感からスピード違反等の危険な運転が原因での事故が発生しやすい傾向にあります。
事故を起こした時も慌てずに、110番通報したり、怪我人がいる場合は119番通報することが大切です。
そういった措置を誤ると、ひき逃げ等の容疑で警察に逮捕される可能性があるので注意してください。
三重県内で警察に逮捕された場合
この連休中に、ご家族が三重県内の警察署に逮捕された方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルは、24時間、年中無休で対応していますので、お時間を気にせずお気軽にお電話いただければ、その状況に応じて最善のサービスを提案させていただきます。
なお三重県外の方からでもご予約をお受けすることができますので、三重県に旅行中のご家族が何か事件に巻き込まれた場合でもご利用いただくことができます。
初回接見サービスについては ⇒⇒こちらをクリック
連休中は、すぐに動いてくれる刑事弁護人が見つかりにくい状況にあります。このコラムをご覧の方で、三重県内の刑事事件でお困りの方、三重県内の警察署にご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、迷わず
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
【解決事例】児童ポルノ製造罪で罰金刑に 略式起訴について
【解決事例】児童ポルノ製造罪で罰金刑に 略式起訴について
児童ポルノ製造罪で罰金刑になった事件の解決事例を参考に、略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の流れ
事件の概要(児童ポルノ製造)
契約社員のAさんは、スマートホンのゲームアプリで知り合った当時16歳の少女とSNSを通じて仲良くなり、メールをやり取りする中で、少女に裸の写真を撮影させて、その写真をメールで自分に送信させました。
事件の発覚と警察の捜査
この出来事からしばらくして少女との連絡は途絶えてしまいましたが、1年以上して、急に三重県津南警察署の捜査員がAさんの自宅を訪ねてきました。
自宅の捜索を受けてスマートホンや、パソコン等の通信機器が押収されたAさんは、その後、警察署に任意同行されて取調べを受けました。
少女のスマートホンに裸の写真が保存されていることに気付いた親が警察に相談して事件が発覚したようで、Aさんは事実を認めていました。
略式起訴による罰金刑
Aさんの弁護人は、警察に対して少女の親と示談交渉すべく連絡先の開示を求めましたが、少女の親がこれを拒んだことから、謝罪等を行うことができませんでした。
その間に検察庁に呼び出されたAさんが、略式起訴による手続きに同意したことから、Aさんは略式起訴されて罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
略式起訴による罰金刑
警察が捜査する犯罪(法律)のほとんどに法定刑(罰則規定)が定められています。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、比較的軽微な事件で、100万円以下の罰金若しくは科料相当の事件については、正式な裁判が開かれることなく、簡易裁判所からの略式命令によって、指定された金額の罰金(科料)を納付すれば手続きが終了します。
この手続きについて検察庁のHPでは「検察官の請求により、簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な事件)100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について、被疑者に異議のない場合、正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。簡易裁判所において、略式命令が発せられた後、略式命令を受けた者(被告人)は、罰金又は科料を納付して手続を終わらせるか、不服がある場合には,正式裁判を申し立てる(略式命令を受け取ってから14日間以内)ことができます。」と説明しています。(検察庁のホームページから引用)
このコラムをご覧の方で、児童ポルノ製造罪でお困りの方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
【解決事例】元彼女から「傷害罪」と「児童ポルノ製造罪」で訴えられた
【解決事例】元彼女から「傷害罪」と「児童ポルノ製造罪」で訴えられた
別れ話のもつれで、元彼女から「傷害」と「児童ポルノ製造」で訴えられた事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
大学生のAさんは、大学1年生(18歳)の彼女と2年間近く交際していましたが、彼女の浮気が発覚し別れることとなりました。
そして彼女と別れ話をしている際にAさんは、彼女の頬をビンタしていました。
別れた後に、元彼女が医師の診断書と共に三重県鈴鹿警察署に被害届を提出したことから、Aさんは、警察署に呼び出されて取調べを受けることになりました。
また取り調べの際に、警察にスマートホンを押収されたAさんは、このスマートホンに保存していた、彼女と交際していた時に撮影していた元彼女の裸の画像が警察に見つかってしまい、児童ポルノ製造の疑いでも取調べを受うることになりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
「傷害罪」について
どんな理由があっても、手を出してしまえば「暴行罪」が成立してしまい、その暴行によって相手が怪我をすれば「傷害罪」となります。
刑法第204条に規定されている通り、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しいものですが、実際にどういった刑事罰が科せられるのかは、暴行に至る動機や、暴行の程度、そして相手の傷害の程度が考慮されて判断されるので、被害者側に落ち度がある場合は、処分が軽減されることもあります。
実際に今回の事件でAさんは、元彼女の浮気に腹を立て、元彼女の頬をビンタするという暴行をはたらき、元彼女を怪我させていますが、不起訴となっています。
「児童ポルノ製造罪」について
児童買春・児童ポルノ処罰法では、児童ポルノの製造を禁止しています。
児童ポルノとは、児童(18歳未満)のわいせつな画像や動画のことで、単なる裸の写真も、児童ポルノと認定される可能性が高いです。
今回の事件でAさんは、撮影当時まだ17歳だった元彼女の裸を、スマートホンで撮影し、その画像を保存していました。
Aさん曰く、元彼女の同意を得て撮影していたようですが、児童の同意の有無に関わらず、こういった行為は児童ポルノ製造罪となります。
児童ポルノ製造罪の法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、製造するまで経緯や、児童との関係、児童ポルノの製造目的、製造した児童ポルノの数など様々な事情が考慮されて処分が決定します。
今回の事件でAさんは、元彼女の同意を得た上で、遊び半分で撮影し性的な意図がなかった上に、撮影した数も少なく、すでに消去していたことから、児童ポルノ製造罪についても、不起訴になっています。
このコラムをご覧の方で、「傷害罪」や「児童ポルノ製造罪」で警察に訴えられた方、「傷害罪」や「児童ポルノ製造罪」にお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談のご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
【解決事例】近鉄山田駅構内の盗撮事件で不起訴を獲得
【解決事例】近鉄山田駅構内の盗撮事件で不起訴を獲得
近鉄山田駅構内の盗撮事件で不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは、近鉄山田駅構内のエスカレーターにおいて、スマートホンを利用して女性のスカート内を盗撮しました。
Aさんは、被害に気付いた女性に腕を掴まれトラブルになっているところを警察に通報され、現場に駆け付けた三重県松阪警察署の警察官に逮捕されました。
スマートホンには女性のスカート内を撮影した映像が残っており、Aさんは、警察署の取調べでは事実を素直に認めていました。
また逮捕翌日に、自宅を捜索されたAさんは、自宅のパソコンに保存していた過去の盗撮画像も警察に発覚してしまいましたが、勾留されることなく逮捕の二日後には釈放されました。
弁護士が、近鉄山田駅構内で起こした盗撮事件の被害者と示談したことによって、余罪については事件化されることなく、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
近鉄山田駅構内の盗撮事件
近鉄山田駅構内の盗撮事件は、三重県の迷惑防止条例違反となります。
三重県の迷惑防止条例では、三重県内の盗撮行為について、第2条2項2号で「通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること。」と規定しており、これに違反し、有罪が確定すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
他府県の迷惑防止条例では、盗撮の規制場所が限定されている場合もありますが、三重県の迷惑防止条例では、規制場所の制限はなく、三重県内いかなる場所においても、盗撮すれば条例違反で処罰の対象となります。
不起訴
不起訴とは、検察官が控訴を提起しないことです。
つまり不起訴になれば、刑事罰が科せられることはなく、前科も付きません。
一言で不起訴と言いましても不起訴にはいくつか種類があります。
(1)嫌疑なし
被疑者(犯人)でないことが明白な時や、被疑者(犯人)とする証拠がないことが明白な時
(2)嫌疑不十分
嫌疑なしほどではないが、被疑者(犯人)とする証拠が乏しい時
(3)起訴猶予
被疑者(犯人)とする証拠はある程度存在するが、様々な事情を考慮して、検察官が、起訴する必要がないと判断した時
等が主な不起訴理由です。(これらの他にも不起訴理由は存在します。)
被害者との示談で不起訴
Aさんの場合は、被害者との示談が成立したため、起訴猶予による不起訴が決定しました。
盗撮事件の場合、被害者との示談が成立すれば、ほとんどの場合で不起訴となりますが、Aさんのように余罪が複数ある場合は、一人の被害者と示談が成立しても起訴される可能性があるので注意が必要です。
このコラムをご覧の方で、三重県内の盗撮事件でお困りの方、盗撮事件で不起訴を目指しておられる方がいらっしゃいましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
【解決事例】強制性交を疑われて取調べを受けている方をサポート
【解決事例】強制性交を疑われて取調べを受けている方をサポート
強制性交を疑われて取調べを受けている方をサポートして不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
Aさんは、出会い系アプリで知り合った20代の女性と会い、同意のもとで、三重県名張市のホテルで性交渉しました。
Aさんは、性交渉後に女性から金銭を要求されたのですが、それを断ったところ、女性は「Aさんに無理矢理性交渉された。」と、三重県名張警察署に強制性交等罪で被害届を提出しました。
Aさんは、三重県名張警察署から呼び出しを受け、不拘束で警察の取調べを受けて、厳しく追及されていましたが、弁護士が徹底したサポートを行いました。
その結果、否認事件として検察庁に送致されたものの不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
強制性交等罪
強制性交等罪は、刑法第177条に規定されている犯罪で、かつての強姦罪です。
強制性交等罪は、被害者が13歳以上の場合と、13歳未満の場合で内容が異なります。
13歳以上の場合は、暴行または脅迫を用いて性交(肛門性交、口腔性交を含む)した場合に成立し、13歳未満の場合は、暴行や脅迫の有無に関わらず、性交した時点で成立します。
今回、Aさんを訴えた女性は20代ですので、強制性交等罪が成立するには、性交の手段として、Aさんが女性に対して暴行や脅迫をはたらいていなければなりませんが、Aさんは、女性と出会ってから一緒にホテルに移動し、そこで性交するまで、女性と争いは一切なかったとのことです。
ただ性交後に急に女性から現金を要求されて、それを断ると女性が怒って一人でホテルを飛び出したようです。
しかし警察は、二人きりになったホテルの中でAさんが女性を脅迫したと疑っているようでした。
取調べをサポート
Aさんは、警察署の取調べで何度も同じことを聞かれて精神的に滅入っていました。
そういう状態に陥ってしまうと、やってもいないことを自白する方もおり、非常に危険な状態であることから、弁護士は取調べの前後にAさんと細目に連絡を取り、取調べに対するアドバイスだけでなく、Aさんを精神面からサポートしました。
しばらく取調べは続きましたが、最終的に警察署ではAさんの否認の供述調書しか作成されずに済み、事件は検察庁に書類送検されました。
そして担当の検察官は、Aさんを一度取り調べた後に不起訴を決定したのです。
このコラムをご覧の方で、三重県の警察署に無実の罪で取調べを受けている方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
保釈について解説 保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験開始
保釈について解説 保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験開始
保釈中の被告人の逃亡防止のためGPSを装着する実証実験が開始されることを参考に、保釈の制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始
4月5日付けの讀賣新聞朝刊によりますと、保釈中の被告人の逃亡を防止する措置として、今後、海外逃亡するおそれのある被告人には、GPSを装着する運用が開始される見通しです。
まだ実証実験の段階で、具体的にどのような被告人が対象になるのかや、どの程度まで監視されるのか、そもそもどの様なGPS端末装置を使用するのか等まで決定していませんが、2016年の運用開始を目指して今後実証実験が繰り返されそうです。
そこで本日は、保釈の制度について解説します。
(本日のコラムは、4月5日付の讀賣新聞朝刊を参考にしています。)
保釈
保釈とは、起訴された後に使うことのできる制度で、保釈請求が認められれば、保釈保証金、いわゆる保釈金を納付することで身体拘束から解放されます。
手続きの流れについては、まず裁判所に対して「保釈の許可を出してください」という保釈請求を行う必要があります。
保釈請求は被告人自身はもちろん、その親族なども行うことが可能ですが、法律の専門知識を要するので、刑事事件に強い弁護士に任せた方がよいでしょう。
裁判所に対して保釈を請求すると、裁判所は検察官の意見も確認します。
裁判所は、保釈請求書及びその添付書類と、検察官から提出された書類、検察官の意見などを参考に、保釈を許可するかどうかを決めます。
裁判所が保釈を許可すると同時に保釈保証金の金額が決定し、その金額を裁判所に納付すれば、被告人の保釈手続きが開始されます。
保釈保証金(保釈金)
なお、裁判所に納付した保釈保証金(保釈金)は、保釈された際に裁判所から付される保釈の条件に違反することなく裁判が滞りなく終了すれば、全額返還されます。
逆に、保釈期間中に逃亡したり、保釈の条件に違反したりして保釈が取り消されたり、裁判に支障が出たりした場合は保釈金は没収されてしまいます。
保釈保証金(保釈金)は、刑事裁判に被告人がきちんと出廷し、その後の刑事裁判に支障が出ないようにするための担保となります。
保釈保証金(保証金)の金額
刑事訴訟法で、保釈保証金(保釈金)の金額について「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない」と定められており、150万円から300万円が相場だと言われています。
しかし時には、とんでもなく高額な保釈保証金(保釈金)が決定されることもあります。
過去の高額な保釈保証金は、一番がハンナン牛肉偽装事件の被告人で20億円で、2位は日産会自動車会長特別背任事件や、指定暴力団六代目山口組若頭による恐喝事件の被告人等で15億円となっています。
保釈に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの弁護活動を行い、事件を解決に導いてまいりました。
その中で、多くの保釈を獲得してきた実績がございますので、三重県内で、身体拘束を受けている方の保釈を希望されるのであれば、是非一度
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
【少年事件】まもなく施行 少年法が一部改正
【少年事件】まもなく施行される一部改正された少年法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
成年年齢を18歳に引き下げる改正民法の施行にともない、少年法の一部が改正されて、本年4月1日より施行されます。
本日は、まもなく施行される少年法の改正ポイントを少年事件を専門に扱っている弁護士が解説します。
「特定少年」の新設
これまでの少年法では、20歳未満が「少年」と定義され、少年法の適用を受けていました。
「少年」の定義に関しては改正後も変わりありませんが、18歳、19歳は「特定少年」と位置付けられて、17歳未満とは異なる手続きがとられます。
原則逆送事件の範囲拡大
これまでは、犯行時の年齢が16歳以上で故意の犯罪行為によって被害者を死亡させる事件を起こした少年が、原則逆送事件の対象となっていました。
改正後は、これに加えて死刑、無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件を起こした特定少年(犯行時の年齢が18歳、19歳)も原則逆送事件の対象となりました。
原則逆送事件の範囲が拡大されたのは、18歳、19歳の特定少年は、責任のある主体として位置付けられているため、16歳や17歳の少年よりも広く刑事責任を負わせることが適当だとされているからです。
原則逆送事件の対象となる事件は、これまで殺人罪や、傷害致死罪、危険運転致死罪等でしたが、これらに強盗罪や、現住建造物等放火罪、強盗罪等が加わります。
罰金以下のみに当たる罪の取り扱い
これまでは罰金以下のみに当たる罪を犯した少年の検察官送致は認められていませんでしたが、改正後は、特定少年に対しては、刑事処分相当であれば検察官に送致するものとされ、罰金以下に当たる罪についても検察官送致の対象となりました。
つまり特定少年の場合、犯してしまった犯罪(罪)に関わらず、検察官に送致される可能性が高まったことになります。
特定少年はぐ犯少年が適用されない
これまで犯罪(罪)を犯していない少年に関して、ぐ犯を理由に家庭裁判所で審理の対象となって保護処分を受けることがありましたが、改正後、特定少年に関しては、ぐ犯少年の規定が適用されることはありません。
これは審判時に特定少年に達しているかどうかが基準となるので、17歳時にぐ犯を理由に家庭裁判所に送致されても、少年審判前に18歳となった場合は、特定少年であることを理由に少年審判を受けることはありません。
推知報道について
少年法では、犯罪を犯してしまった少年の更生と保護を理由に、報道から事件を起こしてしまった少年がどこの誰であるかということを推測できるような報道(推知報道)を禁止しています。
しかし改正後は、特定少年に関しては推知報道の禁止から除外されます。
これは特定少年時に犯罪(罪)を犯した少年については、起訴された場合に、推知報道されることを意味しています。
本日は、4月から施行される改正少年法の主な改正ポイントについて解説いたしました。
この他にも、今回の改正によって変更されている内容があるので詳しくは
こちら⇒⇒クリック
で解説しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
三重県名張市の性犯罪 準強制性交等罪で逮捕されたら…
三重県名張市の性犯罪 準強制性交等罪で逮捕されたら…
【三重県名張市の性犯罪】準強制性交等罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
三重県名張市の準強制性交等事件
三重県名張市に住む会社員のAさんは、に準強制性交等の疑いで、三重県名張警察署に逮捕されました。
Aさんは、出会い系サイトで知り合った女性と食事をした後、ホテルで性交したのですが、女性は当時とても酔っており、性交に同意してはいなかったと言っているそうです。
Aさんとしては、女性が酔っていたのは分かっていたが、性交をする際にも、明確に抵抗されなかったので、同意があったものと思っていました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、すぐに接見に行ってくれる刑事事件専門弁護士に連絡しました。
(フィクションです)
準強制性交等罪とは
準強制性交等罪は、平成29年の改正刑法により「準強姦罪」から改正された罪です。
準強制性交等罪は、暴行・脅迫の手段を用いずに、被害者の抵抗困難な状態を利用して、性交等を行う場合を処罰することとしています。
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
刑法178条1項は、準強制わいせつ罪について規定しており、同上2項が準強制性交等罪について規定しています。
準強制性交等罪は、
(1)人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、
(2)性交等をする
罪です。
(1)人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて
①心神喪失
「心神喪失」とは、精神的または生理的な障害により正常な判断能力を欠く場合をいいます。
例えば、睡眠、酩酊、高度の精神病または精神遅滞により被害者が行為の意味を理解できない場合が「心神喪失」に当たります。
ここでいう「心神喪失」は、責任能力における心身喪失とは異なり、重度の精神薄弱者は、責任能力としての心身喪失状態にあったとしても、性交等の意味を理解している場合には、準強制性交等罪における「心神喪失」には当たらないことになります。
②抗拒不能
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由により心理的または物理的に抵抗が不可能または著しく困難な状態にあることをいいます。
「抗拒不能」に当たる場合としては、行為自体は認識していたが、医療行為だと誤信していた場合や畏怖状態に陥っている場合などが挙げられます。
心神喪失・抗拒不能の程度については、完全に不可能であることまでは求められず、犯行が著しく困難であればよいとされています。
心身喪失・抗拒不能に「乗じ」とは、既に被害者が心身喪失・抗拒不能の状態にあることを利用することを指します。
例えば、泥酔している被害者に対して、性交等を行う場合です。
また、心神喪失・抗拒不能に「させ」とは、犯人が暴行・脅迫以外の手段で抗拒不能の状態を作り出す場合や、暴行・脅迫時には性交等の故意がなかった場合をいいます。
典型例としては、被害者に睡眠薬を飲ませて、眠り込んだ被害者と性交等を行う場合があります。
加えて、準強制性交等罪の成立には、被害者が心身喪失・抗拒不能の状態にあることの認識が必要となります。
被害者が情婦であると誤信したため抗拒不能状態にあることの認識がなかった場合は、準強制性交等罪は成立しません。
また、被害者の同意があるものと誤信していた場合も、故意がないことから、準強制性交等罪は成立しないこととなります。
準強制性交等罪で逮捕されたら
準強制性交等罪で逮捕された場合、逮捕後勾留される可能性は高いと言えます。
事件の重大性や、被害者との接触可能性、逃亡のおそれなど、様々な要素が考慮され、例え、被疑者が身体拘束されることにより被り得る損害を考慮したとしても、なお、勾留することの必要性が認められる場合が多いからです。
しかし、勾留請求を行う検察官や勾留の判断を行う裁判官は、その判断を行う時点では被害者に有利な事情を知らないということもあります。
そのため、逮捕されたら、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士は、迅速に被害者に有利な事情を収集し、勾留が決定する前に、被疑者を勾留する必要がないことを客観的な証拠に基づき、検察官や裁判官に説得的に主張することを通じて、早期に釈放となるよう働きかけます。
また、容疑を認める場合には、すぐに被害者との示談交渉に着手するよう努めます。
被害者がいる事件では、被害者との示談が成立しているか否かといった点は、検察官が起訴・不起訴の判断をする際や、裁判官が言い渡す刑罰を決める際にも考慮されますので、非常に重要です。
示談に応じてもらえるかどうかは、被害者の意思に寄るところですが、交渉窓口となる弁護士の交渉手腕にも問われると言えるでしょう。
三重県名張市の刑事事件に強い弁護士
ご家族が準強制性交等罪で逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。