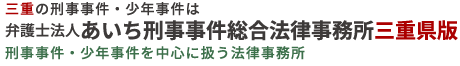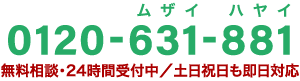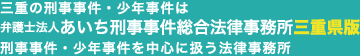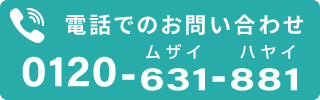Archive for the ‘未分類’ Category
保釈に強い弁護士
保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
保釈中に海外に逃走したカルロス・ゴーン氏の報道に、日本中が驚かされました。
刑事事件に馴染みのない方でも保釈という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、保釈とはどのような制度なのかまで詳しく分からない方がほとんどではないでしょうか。
そこで本日は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が「保釈」の制度について解説します。
~「保釈」とは~
刑事事件を起こしてしまい逮捕され、勾留が付いた後に起訴された被告人が裁判で判決が出るまでの間に釈放されることを保釈といい、この手続きは刑事訴訟法に規定されています。
身体拘束を解かれるという点では「釈放」と同じですが、逮捕や勾留期間中に釈放される手続きとは異なり、保釈の場合は、裁判官が保釈を認めた上で保釈金を裁判所に納付しなければ釈放されません。
裁判所に納付した保釈金は、保釈後の刑事手続き(刑事裁判)が終了すれば返還されますが、保釈中に問題を起こして保釈が取り消された場合は、返還されません。
つまり保釈金は、保釈によって釈放された被告人を刑事裁判に出廷させて、保釈後の手続きを担保する役割があるのです。
~保釈の種類~
一言で「保釈」といっても、保釈にはいくつかの種類があります。
ここでは「保釈」の種類を解説します。
◇必要的保釈◇
権利保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
以下の場合を除いては、裁判官は保釈の請求があった場合、保釈を許さなければなりせん。
1死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき
2被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
3被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
4被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6被告人の氏名又は住居が分からないとき
保釈を請求したときに上記の事由に当てはまらなければ、保釈は必ず認められます。
◇職権保釈◇
こちらは裁量保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。
「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」
職権保釈は必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく、条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
そこで、必要的保釈が認められない場合でも裁判官の判断で保釈が認められる可能性があります。
弁護人は釈放後の住所が定まっていることや監督者がいることを主張し、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明したり、身体拘束が長引くことによる自身や家族、会社などの不利益を主張していったりすることにより、保釈が認められるように活動していきます。
◇その他◇
上記の必要的保釈、職権保釈のほかに義務保釈といわれるものがあります。
この義務保釈は刑事訴訟法91条に規定されており、勾留による拘禁が不当に長くなったときに請求があれば保釈を許さなければならないと規定されています。
~保釈保証金(保釈金)~
保釈が認められた場合、定められた保釈保証金、いわゆる保釈金を納めなければなりません。
この保釈保証金については判決が出ると返還されるのですが、保釈の際に付された条件に違反したり、罪証隠滅を行ったり、逃亡したりすると保釈は取り消され、保釈保証金についても没収されてしまうことになります。
報道によりますと、ゴーン氏には、保釈時の条件として海外渡航が禁止されており、そのため弁護士がパスポートを保管していたようですので、すでに保釈は取消されているようです。
おそらく保釈時に納付した保釈金も没収されて、今後、ゴーン氏のもとに返還されることはないでしょう。
保釈は被告人本人や法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹なども請求することはできますが、前述の様に様々な要件や事情が考慮されることになるので、やはり専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、保釈に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
保釈に関する法律相談:初回無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
ドローンの飛行が航空法違反に
ドローンの飛行での航空法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県津市に住む会社員のAさんは、1ヶ月ほど前にドローンを購入しました。
Aさんは、山登りの様子をユーチューブに投稿する趣味を持っており、空撮するためにドローンを購入したのですが、週末の山登りに備えてドローンがきちんと起動するか確認するため、マンション敷地内にある公園から、ドローンの飛行テストをしました。
その様子を見ていた近所の人が110番通報したらしく、Aさんは、三重県津南警察署の警察官によって、警察署に連行されてしまいました。
ドローンを購入した際に、航空法によってドローンの飛行が制限されていることを知っていたのですが、今回のテスト飛行が違法になるとまで考えていませんでした。
(フィクションです)
◇ドローン◇
無人飛行機を指す用語で、これまで企業が利用していましたが、価格が安い一般人向けの機種が多く販売されるようになり、最近では、様々な分野で多くの方々に利用されています。
ドローンの利用者が増えるにしたがって、ドローンによる事件や事故も多発するようになったことから、数年前に航空法が改正されて、ドローンの飛行が厳しく規制されるようになりました。
◇航空法◇
航空法ではドローンの飛行について以下のような規制が設けられています。
①地表、水面から150メートル以上の高さの空域での飛行禁止
②空港周辺空域での飛行禁止
③日出前、日没後の飛行禁止
④目視外飛行の禁止
⑤第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との距離が30メートル未満での飛行禁止
⑥祭礼や縁日等、人が集まる催し場所での飛行禁止
⑦危険物を輸送するための飛行禁止
⑧ドローンから物を投下する行為
◇罰則規定◇
上記したように航空法で規制されている禁止飛行を行った場合、警察の捜査を受けることになり、検察庁に送致される可能性があります。
そして有罪が確定すれば50万円以下の罰金が科せられます。
◇これまでのドローン事件◇
航空法でドローンの飛行が規制されてからそれほど期間がありませんが、これまでドローンの違法飛行が何件か事件化され、略式罰金等の処分を受けた方がおり、昨年は、東京都内などで逮捕者が出ています。
それでは、これまで摘発された、ドローンの違法飛行事件を紹介します。
~催し場所での違法飛行~
人が多く集待っている花火大会の会場においてドローンを無許可で飛行させた容疑で、ドローンを操作していた男性が警察に検挙されました。
ドローンの違法飛行による実害はありませんでしたが、花火大会を警備していた警察官が飛行するドローンを発見して男性を検挙したようです。
男性は、航空法違反で検察庁に書類送検されました。
~無許可飛行~
イベント会場でドローンから観客にお菓子をまく際に、高度約10メートルからドローンが墜落し、観客の女児らに軽傷を負わせました。
ドローンを飛行させたのは、ドローン事業会社の男性で、事前に、ドローンからお菓子を投下する許可を経ていたそうですが、許可を得た以外のドローンを飛行させたとして航空法違反が適用されたようです。
この事件でドローンを飛行させた男性は、略式起訴されて罰金20万円の刑が確定しています。
~ドローンの違法飛行で逮捕~
罰金刑の規定しかない航空法違反事件では、基本的に警察の捜査は任意で行われ、よほどのことがなければ逮捕されることは滅多にありません。
しかし、公園で無許可でドローンを飛行させた容疑で、警察の捜査を受けた男性は、その際に、証拠品であるドローンの任意提出を拒んだり、捜査関係書類に自署欄に虚偽の氏名等を記載したことから、証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕されたようです。
◇ドローンが刑事事件に発展◇
ドローンの飛行は、航空法違反だけでなく、道路交通法違反や電波法違反などの刑事事件に発展するだけでなく、プライバシーの侵害等で民事事件に発展する可能性もあります。
ドローンを飛行させる際は、ルールを遵守し、安全に十分に配意することをお勧めします。
三重県津市の刑事事件でお困りの方、ドローンの違法飛行で警察の捜査を受けておられる方は、三重県で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
【ネット犯罪②】三重県のネット犯罪に強い弁護士
前回に引き続き、三重県のネット犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)違反◇
不正アクセス禁止法では、不正アクセス行為等を禁止するとともに、違反行為について罰則などが定められています。
~不正アクセス行為の禁止~
◇他人の識別符号を悪用する行為(不正アクセス禁止法2条4項1号)◇
他人の識別符号を悪用することにより、本来アクセスする権限のないコンピューターを利用する行為が禁止されています。
簡単に言うと、他人のIDやパスワードによる不正ログインを思い浮かべていただければ、わかりやすいと思います。
◇コンピュータプログラムの不備を衝く行為(不正アクセス禁止法2条4項2号、3号)◇
アクセス制御のプログラムの瑕疵、アクセス管理者の設定上のミス等の安全対策上の不備、いわゆるセキュリティホールを利用して、システムに侵入する行為を禁止しています。
不正アクセス行為の禁止に反した場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(不正アクセス禁止法11条)。
~他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止~
不正アクセス行為の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得する行為が禁止されており、これに違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(不正アクセス禁止法4条、12条1号)。
不正アクセス行為の用に供する目的には、取得者自身に他人の識別符号を用いて不正アクセス行為を行う意図がある場合のほか、第三者に不正アクセス行為を行う意図がある場合に、そのことを認識しながら、当該第三者に識別符号を提供する意図を持って取得する場合もこれに該当します。
取得とは、識別符号を自己の支配下に移す行為をいい、識別符号を再現可能な状態に記憶することを含みます。
~不正アクセス行為を助長する行為の禁止~
業務その他正当な理由による場合を除いて、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならないとされており、これに違反した場合には、1年以上の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(不正アクセス禁止法5条、12条2号)。
~他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止~
不正アクセスを防止するために、不正に取得された他人の識別符号が不正アクセス行為の用に供する目的で保管する行為が禁止されており、これに違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(不正アクセス禁止法6条、12条3号)。
~識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止~
いわゆるフィッシング詐欺を規制する規定で、これに違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(不正アクセス禁止法7条、12条4号)。
◇ネット犯罪事件における弁護活動◇
~不起訴・無罪の主張~
警察等の捜査当局が取締りを強化しているとはいえ、ネット犯罪は、インターネット上という仮想空間の中で行われるため、犯人を特定するのは他の犯罪に比べ非常に困難な場合があります。
複数のサーバーをたどることで、第三者に成りすますことも容易であるため、全く身に覚えがないことで突然逮捕されてしまう恐れすらあります。
そのような場合は、自分が無実であることを強く訴えていくほかありません。
しかし、ネット犯罪は、証明し難い犯罪であるからこそ捜査機関が強引な取り調べによって自白を迫る可能性があります。
しかし、ネット犯罪容疑での取調や身体拘束の辛さに負け、嘘の自白をしてしまえば、それこそ取り返しのつかない事態となる恐れがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、取調べ対応についてしっかりとアドバイスを行うとともに、違法な取調べに対しては即座に抗議をし、虚偽の自白を作らせません。
そのうえで、ネット犯罪の容疑者とされている方が犯人ではないということを客観的な資料に基づき、捜査機関を説得し、早期の釈放と不起訴処分又は無罪判決による解決を目指します。
~被害者対応及び減刑の主張~
ネット上の犯罪では、それにより被害者が存在することも多くみられます。
そのような場合には、被害者との示談を成立させることが、罪を償う一つの側面であるとして、刑事処分に影響を与えます。
インターネット上で書き込んだ内容が名誉毀損に当たるとされた場合では、親告罪である以上、被害者に許しを得て告訴を取り下げてもらえれば、起訴されることはありません。
被害者が特定の人であるならば、謝罪のみではなく被害弁償なども含み被害者対応を行うべきでしょう。
しかし、ネット犯罪では、不特定の多数に被害を与えているケースもあり、そのようなケースで全ての被害者と示談交渉することはおよそ不可能です。
そのような場合であっても、犯行をするに至った経緯・動機・犯行態様・具体的な被害結果・前科前歴の有無など被疑者・被告人に有利な事情を検察官や裁判官に説得的に主張し、起訴猶予(不起訴処分)や執行猶予付き判決の獲得を目指すこともできます。
三重県のネット犯罪に強い弁護士をお探しの方、ネット犯罪に関しての法律相談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
【ネット犯罪①】三重県のネット犯罪に強い弁護士
三重県のネット犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します
◇ネット犯罪◇
今や、子供からお年寄りまで誰でもインターネットを利用するネット社会になり、スマートフォンの普及により、誰もが、いつでも、どこからでもネットに接続できる環境が整っています。
そんな中、ここ数年で発生件数が急増しているのがネット犯罪です。
近年のインターネットの発達と普及により、コンピューターネットワークというバーチャルな世界で様々なことが可能となるとともに、インターネットを利用して、不正な行為や違法行為が行われるネット犯罪が急増しているのです。
ネット犯罪というのは、インターネット等のコンピューターネットワークを通じて行われる犯罪行為の総称であり、刑事上、特にネット犯罪という名称の犯罪があるわけではありません。
ネットワークは、わが国だけにとどまらず、世界各国のあらゆる地域をも瞬時につなげてくれるほど非常に便利なものですが、その分、システムは複雑となっています。
そのため、これまで警察等の捜査当局は、ネット犯罪に対する取り締まりが困難だとしていましたが、最近は、各都道府県警察に、ネット犯罪専門の部署(サイバー犯罪対策課等)が設立されて、取締りが強化されています。
またネット犯罪の怖いところは、インターネットの利用に当たって、自分が何気なく行った行為が、無自覚のうちに犯罪に該当するということが考えられることです。
そこで本日から2回にわたって、ネット犯罪について特集いたします。
◇不正指令電磁的記録に関する罪◇
正当な理由がないのに、コンピューターウィルスやウィルスプログラムを作成・提供した場合や、コンピューターウィルスをその使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(刑法168条の2)。
正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピューターウィルスやそのプログラムを取得・保管した場合は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります(刑法168条の3)。
◇名誉毀損罪◇
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります(刑法230条)。
インターネット上で書いた内容が、名誉毀損罪の対象になる場合があります。
現在では、FacebookやLINEやツイッターその他の通話チャットアプリケーションなど様々なSNSが、広く利用されています。
そういったSNSに、軽い気持ちで書き込んだ内容が名誉毀損にあたる場合があるので注意しなければなりません。
◇業務妨害罪◇
虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたり、威力を用いて、業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(刑法233条 234条)。
インターネット上での特定の者に対する脅迫や、嘘の犯行予告は、業務妨害罪が成立する可能性があります。
最近では、アルバイト先での悪戯動画をネットに公開した行為が、業務妨害罪に抵触するとして立件された例がありますが、動画投稿サイトの閲覧者数を増やそうとするあまりに、過激な動画を投稿すると、このような事件に発展する可能性があるので注意しなければなりません。
明日は、不正アクセス禁止法と、ネット犯罪における刑事弁護活動について解説します。
三重県のネット犯罪でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
不法投棄事件で警察に呼び出されたら
不法投棄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
Aさんは、引っ越しの際に出た家具等の粗大ゴミの処分にお金をかけるのをもったいなく思い、大量の粗大ゴミを、三重県多気郡明和町の山中に捨ててしまいました。
山林の管理組合がAさんの捨てた粗大ごみを見つけて警察署に相談したために、警察が捜査を開始し、Aの犯行が発覚してしまいました。
Aさんは、三重県松阪警察署から呼び出しを受け、警察署で取調べを受けています。
今後の処分が気になるAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)◇
不法投棄は、廃棄物処理法によって禁止されています。
廃棄物処理法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称です。
廃棄物処理法は、廃棄物を適正に処理することで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物処理に関して、国民、事業者、国や地方公共団体の責務と廃棄物処理方法を定めた法律です。
廃棄物処理法における「廃棄物」とは、占有者が不要になった物、又は他人に有償で売却できないものとされ、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
「産業廃棄物」は、廃棄物処理法で定められている20種類のもので、事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。
「一般廃棄物」は産業廃棄物以外の廃棄物で、一般家庭の廃棄物はこれに該当します。
Aさんが不法投棄した家具類も「一般廃棄物」となるでしょう。
◇一般廃棄物を不法投棄すると◇
不法投棄の刑事処分は意外と厳しい!!
廃棄物処理法では、定められた処分場以外で廃棄物を投棄する行為を「不法投棄」と定義し、不法投棄することを禁止しています。
不法投棄の法定刑は、「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科」と非常に厳しいものです。
ここで注意していただきたいのは、不法投棄では両罰規定が設けられおり、法人の代表者等が法人の業務に関して行った場合、法人に対しては3億円以下の罰金刑が科されることです。
◇その他の廃棄物処理法違反◇
廃棄物処理法では、不法投棄以外にもゴミの処理について様々な規制がされています。
その中の一部を紹介いたしますと、廃棄物処理法の第25条で
①廃棄物処理業の無許可営業
②行政からの命令に違反(「事業停止命令」や「措置命令」など)
③無許可業者への処理委託
④廃棄物の不正輸出
⑤廃棄物の「野焼き」
等が禁止されています。
これらに違反した場合の罰則規定は、不法投棄の法定刑と同じく「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこれの併科」です。
◇不法投棄事件の警察捜査◇
不法投棄については、住民や市区町村からの通報により事件が発覚し、警察が捜査を開始することがほとんどです。
捜査を開始した警察は、現場検証を行ってゴミの投棄場所や投棄量を記録(証拠化)し、その後、ゴミの中から犯人特定に至る手がかりを見つけたり、周辺への聞き込み、防犯カメラ等の確認等により犯人を特定します。
軽い気持ちでしたゴミのポイ捨てでも、不法投棄事件として警察が捜査する可能性があり、過去には、日常生活で出る生活ゴミを指定場所以外の場所に捨てたとして、廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けた方もいるので注意しなければなりません。
ゴミの処理は,各自治体で定められた方法によって適正に処分することをお勧めします。
三重県多気郡明和町の不法投棄事件でお困りの方、不法投棄事件の取調べで警察に呼び出された方は、三重県内の刑事事件に関する法律相談を無料で承っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
【三重県の刑事裁判】津地方裁判所の公判
津地方裁判所の刑事裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事例◇
Aさんは、津市内にある飲食店に、閉店後に忍び込み、レジに入っていた売上金30万円を盗みました。
忍び込んだ飲食店までは、レンタカーで行っており、そのナンバーから被疑者として割り出されたAさんは、建造物侵入罪と窃盗罪で、三重県津警察署に逮捕されました。
20日間の勾留を経て起訴されたAさんは、公判(刑事裁判)の流れや、処分の見通しが知りたくて、保釈後に、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。(フィクションです)
◇公判の概要◇
公開の法廷で行われる刑事裁判を「公判」と言います。
公判は公開の法廷で行われますので、傍聴人が被告人の後ろにいることになります。
なお、裁判の公開は憲法上の要請です。
◇公判手続きの流れ~冒頭手続き~◇
裁判が始まると、実質的な審理を行う前に、最初に形式的な手続きを行います。
これを冒頭手続きと言い、その流れは以下のとおりです。
①人定質問
まず、裁判官の前にいる被告人が、人違いではないかを確かめます。
この手続きを人定質問と呼び、ここで、氏名・生年月日・住所・本籍(国籍)などを尋ねることとなります。
多くの方が本籍地を答えるときに戸惑ってしまいますが、そのような場合には裁判官が起訴状に記載されている本籍地を読み上げ、それで間違いないかを確認することとなります。
②起訴状朗読
次に、検察官が起訴状を読み上げます。
これを起訴状朗読と言います。
③黙秘権告知
その後、裁判官が黙秘権があることを告知します。
黙秘権とは、被告人に対する質問に対し、一切答えなくてもよいという権利です。
もちろん、答えたい質問にだけ答え、答えたくないものには答えないということもできます。
これに加え、裁判官からは、答えた内容は有利にも不利にも考慮されることを注意されます。
ちなみに、被告人質問の際の被告人の受け答えは、それそのものが裁判の証拠として利用されるため、有利不利を問わないのです。
④罪状認否
ここまでを踏まえて、裁判官から、まず被告人に対し、読み上げられた起訴状に間違いがないか確認されます。
これを罪状認否といい、同様の質問は、弁護人に対してもたずねられます。
◇公判手続きの流れ~証拠調べ~◇
①冒頭陳述
まず、検察官が証拠により証明しようとする事実を読み上げます。これを冒頭陳述と言います。
冒頭陳述の内容は、起訴状よりも詳しい犯行態様や、起訴状に記載されていなかった犯行に至る動機、被告人の性格等となります。
②証拠調べ手続
次に、検察官が証拠を提出します。
最初に書類や物が提出され、書類の内容が読み上げられたり、物が裁判官に提示されたりします。
そしてその次に、弁護人が証拠を提出することとなります。
書面の証拠調べが終わると、証人が呼ばれ、証人尋問が行われます。
ただ、被告人が罪を認めている事件で検察官が証人を請求することはまれで、多くは弁護人が請求することになります。
③論告・求刑
証拠調べが終わると、検察官が事件に対する見方などを説明します。
これが論告です。
そして、論告の最後には、被告人に科すべき刑を述べることとなっています。
④最終弁論・意見陳述
そして、弁護側も事件に対する見方を説明します。
被告人が罪を認めている事件であっても、被告人に有利な事情を述べ、少しでも処分が軽くなるように意見を述べることとなります。
弁護人が意見を言い終わると、最後に被告人自身が発言する機会を与えられ、事件に対する意見を述べます。
被告人が罪を認めている事件の場合、ここまでを1回の裁判で終わらせます。
時間としては40分程度になることが多いです。
もちろん、被告人が争っている場合や、認めていても事件が複数個ある場合などには、複数回の裁判が開かれることとなります。
◇公判手続きの流れ~判決~◇
公判の最後に行われるのが、判決言渡しです。
判決言渡しは、被告人が意見陳述をした日とは別の日に行われます。
判決言渡しの日には、判決を言い渡した後、14日以内に控訴できる旨を伝え、そのまま裁判が終了となります。
◇公判手続きの特例~即決裁判手続~◇
上記した公判手続きの流れではなく、判決の言い渡しまでが一日で終わる公判手続きがあります。
それが即決裁判手続きです。
即決裁判手続きは
①軽微な犯罪であること
②事案自体も軽微で明白であること
③証拠調べが速やかに終了すること
④被疑者の同意があること
⑤弁護士が選任されていること
等の条件を満たした場合にのみ行うことができます。
津地方裁判所での公判(刑事裁判)でお困りの方は、これまで多くの刑事裁判において弁護人を務めてきた実績のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
公判(刑事裁判)に関するご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
嫌がらせの注文が偽計業務妨害事件に
偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇ 偽計業務妨害事件の概要 ◇
数ヶ月前にAさんは、桑名市にあるお弁当屋で弁当を購入しましたが、帰宅して食べようと弁当を開けると、注文した弁当と違う種類の弁当でした。
お店に苦情の電話をしたのですが、店側は間違いを認めず、何の対処もしてもらえませんでした。
その事を根に持ったAさんは、お店を困らせてやろうと考え、これまで何度かお店に電話して、お弁当を10個ほど注文し、その弁当を取りに行かないという嫌がらせをしました。
お店にばれないように、注文の電話を掛ける時は携帯電話を非通知にしたり、公衆電話から電話していたのですが、先日、三重県桑名警察署の警察官が自宅を訪ねてきて「弁当屋に嫌がらせした件で話が聞きたい。」と言われて、警察署に連行されてしまいました。
(フィクションです。)
◇ 業務妨害罪 ◇
購入する気のないお弁当を、購入するかのように装ってお店に注文し店員を騙し、お店に損害を与えています。
一見すると人を騙しているので「詐欺罪」が成立するのではないかと考える方もいるかもしれませんが、詐欺罪は、人を騙して財物の交付を受けることによって成立する犯罪です。
今回の事件でAさんは何ら財産的な利益を得ていないので詐欺罪は成立しません。
例えばAさんが「後から代金支払います。」と言って弁当を受け取った上、その支払いをしなかった場合は詐欺罪が成立する可能性があるでしょうが、今回はそうではないので詐欺罪は成立しないのです。
そこでAさんの行為が何の犯罪に抵触するのかを検討すると「業務妨害罪」に該当するでしょう。
詐欺罪が、人の財産を保護することを目的にしている法律であるのに対して、業務妨害罪は人の業務を保護することを目的にしています。
それでは業務妨害罪について詳しく見ていきたいと思います。
業務妨害罪には刑法第233条の「偽計業務妨害罪」と、刑法第234条の「威力業務妨害罪」の2種類があります。
どちらも、人の業務を妨害することで成立する犯罪ですが、その手段、方法によって「偽計」か「威力」かに分類されます。
~偽計業務妨害罪~
「虚偽の風説を流布」又は「偽計」によって、人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害」となります。
「虚偽の風説を流布」とは、簡単に言えば「嘘を言いふらす」ことです。
つまり、お店の不利益となるような、事実と異なることを言いふらして、信用を貶めることによって、人の業務に影響が及べば、偽計業務妨害罪が成立する可能性があるということです。
続いて「偽計」とは、人を騙したり、人の錯誤、不知を利用したり、人を誘惑したりする他、計略や策略を講じることです。
今回の事件のように、弁当を購入する気はないのに、弁当を購入するかのように装って弁当を注文する行為は、店員を騙しているので、偽計業務妨害罪でいうところの「偽計」に当たると考えて間違いないでしょう。
~威力業務妨害罪~
「威力」を用いて、人の業務を妨害すれば「威力業務妨害罪」となります。
威力業務妨害罪でいうところの「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を意味します。暴行や脅迫はもちろんのこと、それに至らないものであっても、社会的、経済的地位・権勢を利用した威迫、多衆・団体の力の誇示、騒音喧騒、物の損壊等およそ人の意思を制圧する勢力一切を含むとされています。
◇ 業務妨害の刑事処分 ◇
業務妨害罪は、偽計業務妨害罪であっても、威力業務妨害罪であっても共に法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば略式起訴による罰金刑になる可能性が非常に高い事件ですが、再犯の場合や、同じ被害者に対して何度も嫌がらせ行為をして悪質性が高いと認められると起訴される可能性も十分に考えられます。
またAさんのような事件ですと、お店側から損害賠償を請求されるおそれもあります。
桑名市の刑事事件でお困りの方、業務妨害罪で警察の捜査を受けておられる方で、刑事処分の軽減を望んでおられる方は、三重県の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談及び初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
インターネットへの書き込みや動画投稿が刑事事件に
インターネットへの書き込みや動画投稿が刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
最近は、スマートフォンやパソコンを利用して、誰もが簡単にインターネット上に、様々な情報を発信できるようになりました。
しかし、書き込みや動画投稿によって、インターネット上に情報を提供することが、その内容によっては刑事事件化される場合もあるので、インターネットを利用している方は気を付けなければなりません。
不確かな情報や、冗談のつもりで投稿したことが、思いもよらない事件に発展し、警察の捜査を受けることもあるのです。
そこで本日は、刑事事件に強い弁護士が、この様なインターネット犯罪について解説します。
◇名誉毀損罪◇
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪行為で、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損することで、その法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
「公然と」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態を意味します。これは、不特定であれば少人数でよく、多人数であれば特定人であってもよいということですので、インターネット上の誰でもが閲覧できる、掲示板や、SNS、動画投稿サイトがこれに該当するでしょう。
「事実の摘示」とは、人の名誉を低下させるおそれのある具体的事実を摘示することをいいます。
その事実は、必ずしも悪事などとは限らないですし、公知、非公知を問いません。
そして、この事実については、真実であったとしても名誉毀損罪は成立しますが、死者の場合は虚偽であった場合のみとなります。
なお、具体的な事実の適示がなく、単に抽象的判断、抽象的批評を加え、人の名誉を低下させる場合は、侮辱罪となります。
「人の名誉」とは、人の社会的評価を意味します。
~事例~
=デマ情報の公表・拡散=
実際に、昨年東名高速道路で発生した、あおり運転による死亡事故の被告人の職場に関して、謝った情報(被告人とは無関係の建設会社を被告人の勤務先とした内容)を、ネットの掲示板サイトやSNSに投稿し、建設会社の名誉を損壊した事実で、複数人が名誉毀損罪で警察の取調べを受け、検察庁に書類送検されています。
今年にも、常磐道におけるあおり運転の犯人をかくまった女性被疑者(犯人隠避罪で逮捕)に関して、女性被疑者が警察に逮捕される前に、事件とは全く関係のない女性を犯人だと誤った情報(デマ情報)をインターネット上に公表したり、そのデマ情報を、不適切な表現を用いてツイッター等で拡散させた行為についても、刑事告訴が検討されています。
◇業務妨害罪◇
業務妨害罪とは、刑法第233条(偽計業務妨害罪)と刑法第234条(威力業務妨害罪)に規定されている犯罪行為です。
この二つの業務妨害罪は、業務を妨害する方法が異なり、偽計業務妨害罪は偽計を用いて業務を妨害することで、威力業務妨害罪は、威力を用いて業務を妨害することです。
「偽計」とは、人を騙(欺罔)したり、人の不知や錯誤を利用したり、人を誘惑することの他、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を意味します。
「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を意味します。暴行、脅迫は当然のこと、それに至らないまでも、社会的、経済的地位、権勢を利用した威力等であって「威力」とみなされる可能性が高いです。
業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
フォロワーや閲覧者数を増やすために、過激な画像をインターネット上に投稿しているのをよく目にしますが、投稿の内容によっては業務妨害罪に該当する可能性があります。
特に最近では、アルバイト従業員が、勤務先での不適切動画をネット投稿したことによって、お店の業務に支障が出たとして偽計業務妨害罪や、威力業務妨害罪が適用された例が多くあるので注意しなければなりません。
◇その他◇
上記した二罪以外にも、投稿の内容が他人を脅迫するような内容であった場合は、刑法第222条の「脅迫罪」が適用されたり、別れた交際相手のわいせつ画像を投稿したことによってリベンジポルノ法違反で検挙されたりした方もいますので、インターネットの掲示板やSNSへの書き込みや、画像、動画投稿には十分に注意してください。
三重県内の刑事事件でお困りの方、インターネットへの書き込みや動画投稿が刑事事件に発展してお困りの方は、三重県内の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
三重県内の刑事事件に関する無料法律相談についてはフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
線路に置き石をしたら往来危険罪
往来危険罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県鳥羽市に住むAさんは、悪戯のつもりで近鉄電車の線路の上に置き石をしました。
走行中の特急電車が石を踏みつけて緊急停車したことから、置き石が発覚し、三重県鳥羽警察署が往来危険罪の容疑で捜査を開始したことが新聞に載っていたのを見たAさんは、警察に逮捕されるか不安です。
(フィクションです。)
◇往来危険罪◇
往来危険罪は、刑法第125条に次のように規定されています。その条文は以下の通りです。
第百二十五条
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
往来危険罪は、汽車・電車・艦船といった現代の主要交通機関の往来の安全を害する行為を、一般の往来妨害よりも重く処罰するものです。
「鉄道」は、レールだけでなく、構造上これと密接不可分の関係にあり、汽車、電車の走行に直接役立っているものすべて、例えば、枕木、鉄橋、トンネルなど、を含みます。
「標識」は、信号機その他運行のための目標を指します。
また、「灯台」とは、夜間、艦船の航行の利便を図るために灯火をもって示した陸上の標識であり、「浮標」とは、艦船の航行上安全か否かや、水の深さを表示する水上の目標、標示物をいいます。
往来危険罪の実行行為は、鉄道、標識、灯台、浮標を「損壊」し、またはその他の方法で、汽車、電車、艦船の往来の危険を生じさせることです。
「損壊」とは、物理的に破壊して、その効用を損なわせることをいいます。
そして、「その他の方法」とは、上の「損壊」以外の方法で、汽車、電車、艦船の往来の危険を生じさせることをいい、その手段や方法は問いません。
判例は、無人電車を使用する行為や、鉄道軌道上に石塊その他の障害物を置くことも「その他の方法」に当たるとしています。
往来危険罪の成立には、交通の妨害を生じさせた程度では足りず、交通機関の往来に危険な結果を生ずるおそれのある状態を発生させることが必要です。
つまり、汽車・電車・艦船の衝突・脱線・転覆・沈没・破壊など交通の安全を害するおそれのある状態が生じたことが必要となります。
この点、判例は、実害が発生するおそれについては、一般的可能性で足り、その必然性や蓋然性は必要ではないとしています。
電車の線路上に石塊をおくことにより、その上を走行した電車が脱線し横転する可能性が生じますので、上記ケースでは、損壊以外の「その他の方法」により汽車・電車の往来の危険を生じさせたと言えるでしょう。
Aさんのように悪戯のつもりで線路に石を置いたとしても、往来危険罪という犯罪が成立する可能性がありますので、注意しなければなりません。
また、往来危険罪を犯し、よって汽車・電車を転覆させたり、破壊した場合、または艦船を転覆・沈没・破壊させた場合には、より重い往来危険による汽車転覆等罪が成立する可能性があります。
鳥羽市の刑事事件でお困りの方、往来危険事件など刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談や初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)まで、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
死体遺棄罪で逮捕
死体遺棄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
三重郡菰野町に住むAさん(28歳)は、自宅の敷地内で発見された息子(9歳)の死体に関し事情を知っていると疑われ、三重県四日市西警察署から任意同行を求められました。そして、Aさんは死体損壊・遺棄罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは接見した弁護士に「殺したのは私ではない。」「殺したのは内縁の夫だと思うが、今どこにいるのか分からない。」などと話しています。
(フィクションです。)
◇死体遺棄罪◇
死体遺棄罪は刑法190条に規定されています。
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以上の懲役に処する
「死体」とは、死亡した人の身体をいい、その一部や臓器でもよく、人の形態を備えた死胎も含まれます。
「損壊」とは、物理的に損傷・損壊することをいいます。
「遺棄」とは、通常は、社会通念上の埋葬とは認められない方法で死体などをその現在の場所から他の場所に移して放棄することをいいます。したがって、殺人犯が、死体を単に現場に放置したまま立ち去ったとしても、一般には、殺人罪のほか死体遺棄罪は成立しません。しかし、その死体について葬祭の義務を負う者が、葬祭の意思なく死体を放置してその場所から立ち去った、あるいは放置し続けていた場合は、不作為による遺棄に当たり死体遺棄罪が成立することがあります。
◇死体遺棄事罪で逮捕されると殺人罪も疑われる!◇
死体遺棄罪で逮捕された場合は、直ちに弁護士に弁護活動を依頼して取調べに対するアドバイスを受けべきです。
なぜなら、死体遺棄罪で逮捕され、死体遺棄罪の件で取調べを受けていたとしても、捜査機関としては「殺人にも関与したのではないか?」と疑い、死体遺棄罪の取調べの中で殺人につて根掘り葉掘り聴いてくる可能性があるからです。
もちろん、この場合、捜査機関が死体遺棄に至った経緯、動機などを解明する趣旨で殺人について関する取調べを行うことは許容されるでしょうが、もやは殺人に関する取調べが主となったと認められる場合は、それは死体遺棄罪ではなく殺人罪での身柄拘束ではないか、つまり別件逮捕・勾留ではないかとも疑わなければなりません。
また、仮に、殺人に関する取調べが許容される場合であっても、殺人に関与していないのであれば取調べで絶対に認める供述をしてはいけません。捜査機関は死体遺棄罪に続いて殺人罪での再逮捕も考えており、長期の身柄拘束を受けてしまうばかりか、いわれのない罪まで負わされてしまう可能性(冤罪の可能性)があるからです。
重大、凶悪事案で再逮捕が活用されるということに理解はできます。
20日間の勾留期間では、起訴するに足りるだけの証拠が集まらないということは現実的にあり得るからです。しかし、ときに、被疑者に対する嫌がらせ、精神的な心の揺さぶりから再逮捕を活用しているとしか思えないケースも存在します。20日間の勾留期間が終わった、保釈が認められやっと釈放されるかと思いきや留置場を出たとたん逮捕される、というケースはいくらでも存在します。被疑者・被告人からすれば、長く、辛い留置場生活にやっとお別れできると思いきや、再び、長く、辛い留置場生活に戻されるのですから、その心情は察するに余りあります。しかし、捜査機関側とすれば、そうした被疑者・被告人の心情を利用して再逮捕を活用してくるのです。
こうした事態を避けるためにも、はやい段階から弁護士のアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、三重郡菰野町で起こった刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。