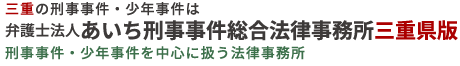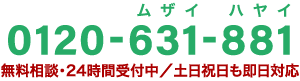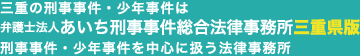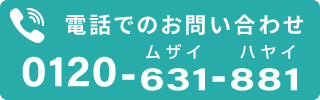Archive for the ‘未分類’ Category
マイナスドライバーを持っているとピッキング防止法違反
マイナスドライバーを持っているとピッキング防止法違反
マイナスドライバーを持っていてピッキング防止法違反となる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAが休日に三重県鈴鹿市内を車で走行していたところ三重県鈴鹿警察署のパトカーに停止を求められました。
Aは特に交通違反をしたわけではありませんでしたが、数日前に起こした事故で車両がへこんでおり、まだ修理をしていなかったため、不審車両であると判断されたようです。
車内検査を受けているとマイナスドライバ―が出てきてAは警察官からピッキング防止法違反になると言われました。
後日、また呼ぶと言われたAでしたが、今後どのようになってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることになりました。
(この事例はフィクションです)
ピッキング防止法違反
正式には「特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律」といい、建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制しています。(以下、ピッキング防止法と表記)
「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」第3条では特殊開錠用具を所持すること、第4条では指定侵入工具を隠して携帯することを禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―やバールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があります。
ドライバーに関する規定
・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上
バールに関する規定
・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上
このように第4条は一般的にも使用する工具が規制の対象となっていることから「隠して携帯」した場合に罰則があります。
隠して携帯するとは人目に触れにくい状態で携帯することを指し、車両内に持っていた場合は隠して携帯していたとされてしまうことがあります。
もちろん、ホームセンターなどで購入したものを持ちかえっている途中や仕事で使用するためなど正当な理由があれば処罰されることはありません。
~聞きなれない罪名は弁護士に相談を~
今回はピッキング防止法というあまり聞きなれない法律による違反事例を紹介しました。
このように、刑法以外の特別法や条例にも罰則規定があり、刑事事件となってしまうことがあります。
代表的なもので言えば、痴漢、盗撮の際の各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例や覚醒剤取締法、道路交通法などです。
聞いたことのない法律の違反だと言われた場合、今後どのようになってしまうのか、どのように対処していけばよいのか、などをインターネットで調べてもあまり出てこないかもしれません。
そのため、ピッキング防止法違反など分かりづらい法律の違反だと言われた場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ピッキング防止法違反などの特別法にも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
建造物等以外放火罪で逮捕
建造物等以外放火罪で逮捕
建造物等以外放火罪で逮捕されてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大学生のA(21歳)は火事の場面を撮影して、SNSに投稿することによって話題となろうと考え、三重県鳥羽市にある公園のゴミ箱に火をつけ、SNSに投稿しました。
その後の捜査の結果、Aが火をつけたことが判明し、Aは建造物等以外放火罪の疑いで三重県鳥羽警察署に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
~放火罪~
「放火行為」とは燃焼する可能性を認識しながら火をつけることをいいます。
直接点火することのみならず燃え移るとわかっていながら別のものに火をつけることや、延焼するとわかっていながらあえて消火措置をとらないことも放火行為に当たる可能性があります。
人が住んでいる建物に火をつけると現住建造物放火罪、人が住んでいない建物の場合は非現住建造物放火罪となります。
そして今回の事例のように火をつけたものが建物でないが、公共の危険を生じさせたときは、建造物等以外放火罪に当たることになります。
建造物等以外放火罪
第110条
1.「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」
2.「前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
※前2条(現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪)
今回の事例のAのように、公園のゴミ箱に放火した場合も建造物等以外放火罪となるでしょう。
~逮捕されたら弁護士派遣を~
今回の事例のように、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、できるだけ早く弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣することができます。
弁護士は、逮捕されている方から事件の詳細をお聞きし、事件の見通しや取調べのアドバイスをお伝えすることができます。
さらに、ご家族からのご伝言をお届けすることが可能です。
~外に出してほしい~
初回接見によって逮捕されている方の状況や事件の見通しをお伝えした後、弁護活動のご依頼を受けることになれば、まずは身体解放に向けて活動していきます。
今回の事例のように、大学生の方が逮捕されてしまった場合、保護者の方からすれば不安は大きなものとなってしまうでしょう。
授業に出られなくなってしまい留年してしまう、事件が大学に発覚し退学になってしまう、将来に向けても就職が困難になってしまう、内定がある場合は取り消されてしまうなどさまざまな不利益が考えられます。
こういった不利益を最小限に抑えるためには、少しでも早い身体拘束からの解放が求められます。
そのためには、できるだけ早い段階で弁護士を選任することが必要です。
弁護士は検察官や裁判所へ意見書を提出するなどして身体解放に向けて活動していきます。
さらに、弁護活動の依頼によって最終的な処分に向けても活動していきます。
刑事事件では、処分が出てからでは間に合わない活動もあります。
そのため、後悔のない事件解決のためには、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
SNSでの話題作りのために行き過ぎた行為で逮捕されてしまうということはたびたび報道もされます。
もし、刑事事件になってしまった場合には、すぐに弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕された場合には、すぐに初回接見をご利用ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
包丁を持ち歩いて銃刀法違反事件
包丁を持ち歩いて銃刀法違反事件
包丁を持ち歩いての銃刀法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県桑名市に住む調理師のA、あるとき仕事で使う包丁のメンテナンスのため、料理用の包丁を鞄に入れて帰宅していました。
するとその途中、三重県桑名警察署の警察官が職務質問でAに話しかけてきました。
そして、所持品検査の際にAの鞄の中から包丁が出てきたことで、警察官から銃刀法違反の疑いがあると言われてしまいました。
仕事道具であり、必要があったからたまたま持ち帰っていたということを説明したのですが、警察官は納得してくれず、警察署に来てほしいと言われてしまいました。
(この事例はフィクションです。)
銃刀法違反
銃刀法は、正式名称「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律で、名前の通り銃砲や刀剣等についての所持や使用等を取り締まっている法律です。
銃刀法では、刃の長さが6センチメートルを超える刃物を正当な理由なく所持することを禁止しています。
銃刀法22条
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」
罰則
銃刀法第31条の18
「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
条文中に「業務その他正当な理由による場合を除いては」とあることから、業務や正当な理由があれば、6センチメートルをこえる刃物を携帯していたとしても銃刀法違反とはなりません。
今回の事例のAは、調理師であり、包丁は商売道具でそのメンテナンスのために持ち歩いていることから、銃刀法違反とはならない可能性が高いです。
しかし、警察官としても調理師だと言っただけで、銃刀法違反に該当する刃物を持ち歩いている者を見逃していると重大犯罪につながってしまう可能性があるので、すぐには納得しないこともあるでしょう。
そのようなときは、刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
後日呼ぶと言われたら
もしも、銃刀法違反を疑われて警察から後日取調べに来てほしいと言われたら、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料での対応で、法律相談を行っています。
無料法律相談では、事件の見通しはもちろんのこと、取調べを受ける際のアドバイスなどもお聞きいただけます。
そのため、警察の取調べを受けなければならないという場合には、取調べの前に、弁護士に相談するようにしましょう。
逮捕されてしまったら
万が一、銃刀法違反の疑いで警察に逮捕されてしまったら、ご家族はすぐに刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスを行っております。
お電話でのお手続きですぐに、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣します。
逮捕されている方から取調べのアドバイスや事件の見通しをお伝えし、ご家族にご報告することができます。
また、ご家族からの伝言をお届けすることもできますので、逮捕されてしまったらすぐに初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
逮捕された方との面会
逮捕された方との面会
逮捕された方との面会について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県伊勢市に住む会社員のAは、あるとき三重県伊勢警察署からの着信を受けました。
三重県伊勢警察署の警察官は、「息子さんを傷害罪で逮捕しました。」と伝えてきました。
息子が逮捕されたと聞いたAは、急いで三重県伊勢警察署に向かいましたが、担当した警察官に「面会できるようになるのは、明後日以降になる」と言われ逮捕された息子と面会することはかないませんでした。
どうすればよいかわからなくなったAは、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話してみました。
(この事例はフィクションです)
逮捕された人との面会
ご家族が逮捕されたと聞かされた場合、すぐにでも直接会って事情を聴きたいと思うのではないでしょうか
逮捕されてしまった後、勾留が決定することになれば、面会をすることは可能ですが、逮捕されてから勾留が決定するまでの間は一般の方が面会できることはあまりありません。
また、もしも勾留決定時に接見禁止が付いてしまうと、勾留決定後も面会することはできないので、逮捕されている方と面会できない状態が続いてしまいます。
しかし、弁護士であればたとえ逮捕されてしまった直後であっても面会することが可能です。
身体拘束を受けている方との弁護士の面会については、刑事訴訟法で規定されています。
刑事訴訟法39条1項
「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」
この条文で注目していただきたいのは、「弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」も面会(接見)が許可されているという点です。
ちなみに弁護人を選任することができる者とは
・被告人又は被疑者
・被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
(刑事訴訟法第30条)
です。
そのため今回の事例のAのように息子が逮捕された場合も含めご家族であれば、弁護士に、弁護人になろうとする者として面会を依頼することができるのです。
初回接見サービス
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、お電話でのお手続きでスピーディに弁護士を逮捕されている方の下へ派遣することができます。
派遣された弁護士は逮捕されている方と面会し、事件の詳細を聞いたうえで、今後の見通しや取調べに対してのアドバイスをお伝えします。
また、ご家族の伝言をお届けすることもできますので、逮捕されている方の励みにもなりますし必要事項を聞くこともできます。
面会終了後は、ご依頼いただいたご家族にご報告させていただき、弁護活動に入ることになれば、身体解放に向けて活動していきます。
逮捕されたと聞いたご家族も不安になることはもちろんですが逮捕されている方の不安や動揺はより大きなものとなります。
弁護士を選任するべきなのか、逮捕されている方は選任を望んでいるのか、どんな事件を起こしてしまったのか、冤罪ではないのか、など今後の行動の指針にするためにも、まずはすぐに弁護士の面会を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護活動を依頼しようか迷っているという段階の方は特に、その判断の手助けにもなりますので、一度お電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
複数の犯罪行為をした場合 ~併合罪~
複数の犯罪行為をした場合 ~併合罪~
併合罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県伊勢市に住むAは、あるとき自宅近くの山で登山をしていたところ一組のカップルと口論になってしまいました。
頭にきたAは、カップルの男性を殴り倒してしまい、男性は傷を負い、気を失ってしまいました。
その様子を見て、恐怖に震えていた女性を見るうちに、Aは性的興奮を覚えてしまい、女性に対して性交を行いました。
性交終了後、すぐに山を下りたAでしたが、後日三重県伊勢警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
Aの家族は弁護士を派遣させるため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所と連絡を取っています。
(この事例はフィクションです。)
傷害罪と強制性交等罪
今回のAは、刑法第204条の傷害罪と刑法第177条の強制性交等罪にあたると考えられます。
2つの罪を犯してしまった場合どのようになってしまうのでしょうか。
刑法第45条では、確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする、と規定されています。
そして、併合罪となった場合の有期の懲役及び禁錮についての処理は刑法第47条に規定されています。
刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」
併合罪についての条文を確認したところで、今回問題となる傷害罪と強制性交等罪の法定刑を見ていきましょう。
傷害罪
「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
強制性交等罪
「5年以上の有期懲役」
刑法第12条で有期懲役は「1月以上20年以下」と定められています。
すなわち強制性交等罪は「5年以上20年以下の懲役」ということになります。
傷害罪の場合の懲役刑の範囲も厳密にいえば、「1月以上15年以下」です。
なお、それぞれの刑について定められている有期懲役の刑において、一番重いものを長期、一番軽いものを短期といいます。
それでは、併合罪の条文通りに当てはめてみましょう。
まず、最も重い刑の長期とは、今回の場合、強制性交等罪の20年ということになります。
この20年にその2分の1を加えると30年ということになります。
これは、傷害罪の15年と強制性交等罪の20年を単純に足した35年より長くはなりませんので、傷害罪と強制性交等罪の併合罪では、「5年以上30年以下の懲役」が法定刑となります。
なお、併合罪における短期の定め方は、併合罪となる罪の短期の中で一番重いものとなります(名古屋高裁 昭28・7・28判決)。
複数の事件がある場合は弁護士に相談を
上記のように、複数の犯罪行為があった場合には、その処断の範囲は条文だけではわかりにくくなってしまいます。
「5年以上30年以下の懲役」という法定刑は、どこの条文にも書いておらず、条文から導き出さねばなりません。
また、複数の犯罪行為の場合に問題になるのは、併合罪だけではありません。
観念的競合や牽連犯となることもありますので、複数の犯罪行為を行ってしまった場合や複数の罪名で警察から疑われているという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、見通しを含めて見解を聞いた方がよいでしょう。
実際に導き出される法定刑の範囲によっては、執行猶予獲得の可能性や、保釈の可能性など事件の見通しが変わってくる場合もありますので、弁護士に依頼をするようにしましょう。
また、今回の事例のように逮捕されてしまった場合には、ご家族の方はすぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。
逮捕されている刑事事件では、手続きに時間制限が設けられているため、後悔のない事件解決に向けては、できるだけ早く適切な対応を取っていくことが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、お電話でのご予約が可能な初回接見の対応をしております。
三重県伊勢市の刑事事件でお困りの方や、そのご家族がおられましたらフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
犯人隠避で逮捕
犯人隠避で逮捕
犯人隠避で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県津市の会社員男性と交際しているA子さんは、この男性と車でデートしている際に、通行していた別の車とのトラブルに巻き込まれました。
このトラブルの際、A子さんと交際している男性は、トラブル相手の顔面を数発殴打する暴行を加えました。
そのままA子さんは、男性と共に逃走したのですが、数日後、テレビのニュースでこの事件が報道されており、A子さんは、交際相手の男性に対して、傷害罪で逮捕状が発付されていることを知りました。
Aさんは、交際相手の男性が警察に逮捕されるのを免れるために、男性に逃走用の資金や、連絡を取り合うのに使用する携帯電話機を渡しました。
しかし、事件から数週間後に、交際相手の男性は逮捕されてしまいました。そして、A子さんも犯人隠避の疑いで警察に呼び出されて取調べを受けています。
(この事例はフィクションです)
犯人隠避罪
刑法第103条に、犯人蔵匿罪と隠避罪が定められています。
この法律は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した犯人や、拘禁中に逃走した犯人の逃走を手助けした場合に適用される法律です。
逃走を手助けする方法として、検挙を免れるための場所を提供すれば「犯人蔵匿罪」となり、蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為をした場合は「犯人隠避罪」となります。
犯人蔵匿罪の行為としては、逃走中の犯人を自宅で匿ったり、潜伏するための部屋を提供することです。
犯人隠避罪の行為には、特に制限がなく、犯人が警察等の捜査当局の逮捕を免れるための一切の手助けが犯人隠避罪に当たる可能性があります。
A子さんのように、逃走資金や、携帯電話機を譲渡する行為の他、逃走用の車両を提供したり、場合によっては、逃走中の犯人と行動を共にすること自体が、犯人隠避罪に該当する可能性があるのです。
またよくある例として「身代わり出頭」も、犯人隠避罪に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の罰則~
裁判で有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されますが、初犯であっても実刑判決の考えられる犯罪です。
~親族による犯罪に関する特例~
刑法第105条で、犯人蔵匿・隠避罪についての特例が定められています。
その内容は、逃走犯人の親族が蔵匿・隠避行為を行っても、刑を免除するといった内容です。
ここでいう親族とは、民法上の「親族」を意味し、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が親族といえます。
当然のことながら、交際相手は、親族には該当しません。
三重県内の刑事事件でお困りの方、犯罪を犯して逃走中の犯人の逃走を手助けしてしまった方、ご家族、ご友人が犯人蔵匿罪、犯人隠避罪で逮捕されてしまった方は、三重県で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、三重県内の刑事事件に関する無料法律相談や、三重県内の警察署に逮捕されてしまった方への初回接見サービスを電話で承っておりますので、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
三重郡川越町の山林に廃材を投棄
三重県川越町の山林に廃材を投棄した廃棄物処理法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇廃材を投棄◇
三重郡川越町で解体業を営んでいるAさんは、業務で出た廃材を捨てる場所に困っていました。
ある日Aさんは、三重郡川越町の人気のない山林に、これらの廃材を投棄して処理しました。
Aさんは、ダンプカーに廃材を運び込んで、重機を使って山中に廃材を埋めたのです。
そうした不法投棄行為をしばらく続けていたところ、地盤が緩んだことが原因で地滑りが起き、Aさんの犯行が発覚してしまいました。
Aさんは廃棄物処理法違反の容疑で三重県警に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
◇廃棄物処理法と産業廃棄物◇
不法投棄事件と聞くと、今回のAさんのような、産業廃棄物を大量に捨てているケースをイメージされる方も多いのではないでしょうか。
廃棄物の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(略称:廃掃法、廃棄物処理法など)という法律が定めています。
この廃棄物処理法の中では、「産業廃棄物」は以下のように定義づけられています。
廃棄物処理法2条4項
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
1号 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2号 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
このうち、廃棄物処理法2条4項1号の「政令で定める廃棄物」については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」という政令で詳しく定められています。
廃棄物処理法施行令2条
法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
1号 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
2号 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
3号 繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
4号 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
4の2 と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第1項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第6号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
5号 ゴムくず
6号 金属くず
7号 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
8号 鉱さい
9号 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
10号 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
11号 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
12号 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第7号及び第10号、第3条第3号ワ並びに別表第1を除き、以下同じ。)
ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第5号ロ(1)、第8号及び第11号、第3条第2号ホ及び第3号ヘ並びに別表第1を除き、以下同じ。)
ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハ及び別表第5を除き、以下同じ。)
ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハを除き、以下同じ。)
ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハを除き、以下同じ。)
ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第5号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ト 前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで及び第5号から第9号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)
13号 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで、第5号から第9号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
かなり多くの項目があって驚かれた方もいるのではないでしょうか。
「産業廃棄物」と聞くと、工場から出た汚泥や汚水、機械ごみのようなものをイメージされる方も多いですが、印刷業などで出た紙類(施行令2条1号)や建設業で出た木くず(施行令2条2号)、さらには畜産業で出た動物の糞尿や死体(施行令2条10号・11号)なども廃棄物処理法上では「産業廃棄物」となるのです。
「産業廃棄物」の範囲は、一般にイメージされるよりも広いことがお分かりいただけたのではないでしょうか。
◇産業廃棄物の不法投棄◇
廃棄物処理法では、以下の条文で不法投棄を禁止しています。
廃棄物処理法16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
これに違反して不法投棄をした場合、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」されることになります(廃棄物処理法25条1項14号)。
産業廃棄物の不法投棄の場合、不法投棄の量の多さや不法投棄による土地への大きさ、不法投棄をすることによって浮かせた経費の大きさ等から、一般人がごみを不法投棄したケースに比べて厳しく処分されることが考えられます。
まずは弁護士に相談し、どういった見通しが考えられるか聞いてみましょう。
◇廃棄物処理法に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、産業廃棄物の不法投棄事件についてのご相談を承っています。
まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
万引きが強盗事件に発展!!
事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇万引きが強盗罪に発展した事件◇
三重県鈴鹿市のドラッグストアで商品を万引きしたAさんは、目撃した警備員から腕を掴まれてました。
Aさんは、とっさに自分の腕を振り回したところ、警備員を引きずり軽傷を負わせてしまいました。
通報を受けて駆け付けた三重県鈴鹿警察署の警察官は、Aさんを強盗致傷の容疑で逮捕しました。
Aさんは、取調べに対して、「腕を掴まれてパニックになった。」と話しています。
Aさんには前科前歴がなく、日ごろから真面目であったため、強盗致傷での逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、非常に驚いています。
(フィクションです。)
◇万引き事件で強盗!?~事後強盗とは~◇
店員に見つからないように、代金を支払わず商品を無断で持ち去る行為は、「万引き」と呼ばれます。
一般的に、万引きは「窃盗罪」に該当します。
しかし、店員や警備員に万引きを目撃され、万引き犯を確保しようとする際に、その店員や警備員に対して暴行を働いて逃げようとした場合には、窃盗罪ではなく事後強盗罪に問われることがあります。
事後強盗罪とは
事後強盗は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をした」場合に成立する罪です。
◇犯行の主体◇
事後強盗の主体は、「窃盗」です。
窃盗とは、窃盗の実行に着手した者をいいます。
窃盗の実行に着手していれよばく、既遂に達している必要はありません。
◇犯行の対象◇
事後強盗の客体に特に制限はありません。
必ずしも窃盗の被害者本人に加えられる必要はなく、逮捕しようとする警察官、追いかけてくる目撃者に対して暴行・脅迫を加えることも事後強盗の対象となります。
◇行為◇
窃盗の現場もしくは窃盗の機会に、暴行・脅迫がなされることが必要です。
つまり、窃盗と暴行・脅迫との間に、場所的接着性、時間的接着性、関連性が必要となるのです。
場所的接着性については、暴行・脅迫のなされた場所が、窃盗の犯行現場またはこれに接着した場所であることが求められます。
時間的接着性については、暴行・脅迫をした時点が、少なくとも窃盗に着手した以降であって、遅くとも窃盗の犯行終了後間もないことが必要です。
また、場所的、時間的に離れている場合でも、被害者に追跡され続けているような場合であれば、暴行・脅迫をしたことと、当該窃盗の事実との間に関連性があると言えます。
暴行・脅迫の程度については、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要です。
◇目的◇
以上の行為を、次のいずれかの目的をもって行ったことが必要となります。
①財物を取り返されることを防ぐ目的
②逮捕を免れる目的
③罪跡を隠滅する目的
目的は内心の問題であるので、その特定に当たっては、客観的な行動に即して判断することになります。
このような目的をもって万引き犯が暴力をふるった場合には、事後強盗罪が成立し、その犯人が相手方を怪我させてしまった場合には、強盗致傷罪に問われることになります。
強盗致傷は、その法定刑が無期または6年以上の有期懲役と、かなり重い罪が科せられる可能性があります。
◇Aさんの場合◇
Aさんは、「腕を掴まれてパニックになった。」と警備員に暴力を振るった理由について話しています。
逮捕を免れるためなどといった目的ではなかったと判断されれば、事後強盗罪は成立しませんので、捜査機関による取調べには適切に対応する必要があります。
また、万引きをしたドラッグストアや、怪我をした警備員への謝罪・被害弁償を行い、示談を成立させることができれば、最終的な処分にも大きく影響することになります。
このような弁護活動は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。
◇刑事事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が事後強盗事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
刑事裁判と判決の確定
刑事裁判と判決の確定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇刑事裁判で有罪判決◇
津地方裁判所で、過失運転致傷罪の罪で有罪判決を受けたAさん。
言い渡された刑は、懲役1年執行猶予3年でした。
Aさんは、この判決がいつ確定して、確定したらどのような効果が生じるのか、公判後に弁護人に質問しました。
(フィクションです)
◇刑事裁判について◇
「裁判」というのは、裁判所または裁判官の意思表示的な訴訟行為のことです。
この裁判は、様々な観点によって次のように分類することができます。
(1)裁判の形式による分類
①判決
裁判所による裁判を「判決」といい、原則として口頭弁論に基づいてなされます。
判決に対する不服申立ての方法は、「控訴」と「上告」です。
②決定、命令
裁判所による裁判を「決定」といい、裁判官による裁判を「命令」といいます。
判決とは異なり、口頭弁論に基づいて行う必要はありません。
「決定」に対する不服申立ての方法は「抗告」、「命令」に対する不服申立ての方法は「準抗告」です。
(2)裁判の内容による分類
①実体裁判
申立ての理由の有無について判断をする裁判を「実体裁判」といいます。
刑事訴訟においては、公訴の理由の有無について判断をする裁判のことを指します。
つまり、有罪判決や無罪判決が実体裁判に当たります。
②形式裁判
「形式裁判」というのは、申立ての有効・無効についてい判断をする裁判のことです。
つまり、手続上の要件が存在しないために不適法だという判断を示すものです。
刑事訴訟法は、形式裁判を「管轄違い」、「免訴」、「公訴棄却」の3つに分けて規定しています。
被告事件について、犯罪の証明があったときは、判決で刑を言い渡すか、もしくは刑の免除をしなければなりません。
有罪判決を言い渡すをするには、「罪となるべき事実」、「証拠の標目」、そして「法令の適用」を示さなければなりません。
「罪となるべき事実」とは、犯罪の構成要件に該当する具体的事実、責任の存在、構成要件の修正形式に当たる事実、処罰条件の存在、共謀共同正犯における「共謀」等をいいます。
「証拠の標目」は、その証拠の同一性を示す標題・種目のことです。
この証拠の標目は、罪となるべき事実について必要となります。
「法令の適用」とは、主文の刑が導き出される法令上の根拠を明らかにし、また未決通算など主文において付随的な処分が言い渡されているときは、その法令上の根拠を明らかにすることをいいます。
また、裁判所は、事実の認定および法令の適用とともに、刑の量定を行わなければなりません。
法定刑から刑種を選択し、加重減軽を行い処断刑を導き出したら、情状などを考慮した上で宣告刑を決めます。
さらに、執行猶予や保護観察を付すか否かも決めます。
一方、被告事件が罪とならないときや被告事件についての犯罪の証明がないときには、裁判所は無罪判決を言い渡さなければなりません。
◇判決の確定について◇
裁判長が公判廷において裁判(判決)を宣告したことをもって、裁判は外部的に成立することになります。
判決を宣告したことをもって直ちに判決が「確定」したとは言えません。
裁判が通常の不服申立方法によって争うことができなくなる状態を「裁判の確定」といいます。
具体的には、上訴期間を過ぎたとき、上訴を放棄・取り下げたとき、上訴棄却の裁判が確定したときに裁判が確定します。
裁判が外部的に成立すると、その裁判を行った裁判所自身に対する拘束力が生じますが、その裁判は不服申立ての結果により覆る可能性もあります。
しかし、裁判が一度確定してしまうと、通常の不服申立方法によっては争うことができなくなります。
無罪または有罪判決がひとたび確定すれば、再び同じ事件で実体審理を受けることはできません。
この原則を「一事不再理効」といいます。
◇刑事裁判に強い弁護士◇
刑事事件を起こして取調べを受けている方、起訴された方、裁判で有罪判決を受けたが量刑に納得いかない方など、刑事事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)まで今すぐご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
交番における業務妨害は何罪?①~公務執行妨害罪~
交番において警察官の業務妨害行為をした場合は何罪となるのか検討するにあたり、特に公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県いなべ市に住んでいるAさん(17歳)は、以前、三重県いなべ警察署の警察官に補導され、その時に夜遅くに出歩かないよう注意されたことを根に持っており、警察官に迷惑をかけてやりたいと思っていました。
そこでAさんは、三重県いなべ警察署の管轄にある交番へ行き、警察官が不在の間に、交番の出入り口に消火器を噴射しました。
これによって、交番はしばらく出入りが困難な状態になってしまいました。
Aさんの犯行を目撃していた通行人が通報し、捜査の結果、Aさんは威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさん逮捕の知らせを聞いた際、警察の邪魔をしたらしいということなのになぜよく聞く公務執行妨害罪ではないのか、もしかしてAさんが不要な疑いを持たれているのではないかと不安に思っています。
(※令和2年4月9日東海テレビ配信記事を基にしたフィクションです。)
交番における業務妨害は公務執行妨害罪ではない?
今回のAさんは、交番へ消火器を噴射したことで逮捕されてしまっていますが、Aさんの両親は、Aさんの逮捕容疑が威力業務妨害罪であることに疑問を持っているようです。
一般のイメージとして、警察官などの公務員に対して何かしてしまった場合、公務執行妨害罪によって逮捕されたり捜査されたりというイメージが強いかもしれません。
ドラマなどでも、職務質問をされた被疑者が暴れて公務執行妨害罪の容疑で取り押さえられる、というようなシーンを目にしたことのある方も多いのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんは、交番に消火器を噴射しているにもかかわらず、公務執行妨害罪の容疑で逮捕されていません。
どうして罪名が異なるのでしょうか。
まず、公務執行妨害罪の条文を確認してみましょう。
刑法第95条第1項(公務執行妨害罪)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
このうち、今回ポイントとなるのは公務執行妨害罪として成立するのが「公務員が職務を執行するに当たり」行われたものである必要があるという点です。
「公務員」とは、文字通り公務員を指しています。
例えば、警察官はもちろん、市役所の職員や、公立の学校の先生や職員もこの対象です。
そして、公務執行妨害罪の条文では、その公務員が「職務を執行するに当たり」暴行や脅迫が行われることで公務執行妨害罪が成立するとされています。
大まかに言えば、これは「仕事をする際に」という意味です。
加えて、この「職務」とは、仕事全てをざっくりと含んでいるわけではありません。
判例では、公務執行妨害罪は「公務員そのものについて、その身分ないし地位を特別に保護しようとするものではなく、公務員によつて行なわれる公務の公共性にかんがみ、その適正な執行を保護しようとするものである」ことから、「その保護の対象となるべき職務の執行というのは、漫然と抽象的・包括的に捉えられるべきものではなく、具体的・個別的に特定されていることを要するものと解すべき」とされています(最判昭和45.12.22)。
ですから、公務執行妨害罪の「職務を執行するに当たり」とは、「ある程度具体的・個別的に特定された公務員の仕事をするに際して」ということになるのです。
今回のAさんの事例を見ると、Aさんは警察官不在の交番に消火器を噴射しています。
対象が交番という建物であり、さらに警察官は不在にしていますから、客体が公務執行妨害罪の客体である「公務員」ではありません。
さらに、先程触れたように、公務執行妨害罪成立のためには、その公務員の「職務」=ある程度具体的・個別的に特定された仕事が行われるに当たって、暴行や脅迫が行わなければなりません。
警察官不在の際におこなわれ、しばらくの間人の出入りが困難になったという状況では、この「職務を執行するに当たり」という条件に当てはまらないと考えられます。
したがって、たしかにAさんは警察の業務妨害行為をしているようですが、公務執行妨害罪にはあたらないと考えられるのです。
ただし、例えば巡回中の警察官に消火器を噴射したような場合や、交番の中で警察官が仕事をしているところに消火器を噴射したような場合には、公務執行妨害罪が成立することになると考えられます。
では、やはりAさんの逮捕容疑である威力業務妨害罪が、Aさんに成立するであろう正しい罪名ということになりそうです。
これがどういった犯罪なのかは、次回の記事で取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務執行妨害事件や威力業務妨害事件といった刑事事件・少年事件のご相談・ご依頼を受け付けています。
Aさんのご両親のように、自分のこどもが逮捕されてしまったが本当に大丈夫なのか、不要な疑いをかけられていないかと心配されている親御さんにも安心してご相談いただけます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。