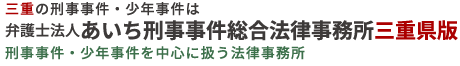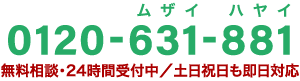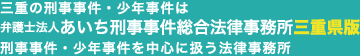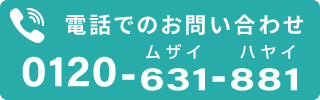Author Archive
大麻栽培による大麻取締法違反事件で逮捕
大麻栽培による大麻取締法違反事件で逮捕
大麻栽培による大麻取締法違反事件で逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県伊勢市に住んでいるAさんは、以前から大麻を使用していましたが、次第に「購入するよりも自分で栽培してしまえばいいのではないか」と考えるようになり、自宅で大麻を栽培するようになりました。
Aさんが大麻を栽培し始めてからしばらくして、Aさんが以前大麻を購入していた売人が三重県伊勢警察署に摘発され、その結果Aさんにも捜査の手が伸びることになりました。
そして、Aさんの自宅に家宅捜索が入り、Aさんが大麻の栽培をしていることが発覚。
Aさんは大麻取締法違反の容疑で三重県伊勢警察署に逮捕されることになり、逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、三重県の刑事事件に対応している弁護士に、大麻栽培による大麻取締法違反事件について相談することにしました。
(※実際の事件を参考にしたフィクションです。)
・大麻の栽培と大麻取締法違反
多くの方がご存知のように、大麻は大麻取締法という法律で規制されている違法薬物です。
大麻取締法では、大麻の所持や輸入などを原則として禁止しています。
今回のAさんは大麻の栽培をしていたようですが、大麻の栽培についても、大麻の栽培についても、大麻取締法で原則禁止されている行為です。
大麻取締法第24条
第1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
大麻取締法第24条第1項に「みだりに」とあるのは、簡単に言えば「むやみやたらに」ということであり、一般の方については単純に栽培や輸入をしただけでも「みだりに」栽培や輸入をしたということになります。
「みだりに」に当たらない例としては、大麻取締法で大麻の取り扱いを許可されている農家や研究者が許可を受けた範囲で栽培などを行うことが挙げられます。
大麻の栽培による大麻取締法違反で注意しなければならないこととしては、同じ大麻の栽培という行為でも、第24条第1項と第2項で刑罰の重さが異なるということです。
第1項では単純に栽培などをした場合が定められており、第2項では営利目的に栽培などを行った場合が定められています。
つまり、大麻の栽培を営利目的=売買などをする目的でしていたかどうかによって刑罰の重さが変わるということなのです。
どういった目的で大麻を栽培していたかということは、あくまで人の内心の問題ですが、当事者の供述だけで判断されるわけではありません。
もちろん、本人がどういった認識で大麻の栽培をしていたのかという話も考慮されますが、例えば、栽培していた大麻の量や販売の履歴の有無など、客観的な事情も考慮した上で営利目的かどうかが判断されます。
ですから、場合によっては、今回の事例のAさんのように自分で使用する目的であったのに、営利目的の疑いをかけられ、本来よりも重い罪に問われてしまう可能性があります。
そういった冤罪を避けるためにも、まずは弁護士に相談し、取調べ等に適切に対応できるようアドバイスを受けることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻栽培などを含めた大麻取締法違反事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
大麻取締法違反事件でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
出会い系アプリで援助交際を募集 出会い系サイト規制法違反で検挙
出会い系アプリで援助交際を募集 出会い系サイト規制法違反で検挙
出会い系アプリで援助交際を募集したとして、出会い系サイト規制法違反で検挙された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
三重県に住むの大学生Aさん(22歳)は、3ヶ月前に、出会い系アプリの掲示板に「本番JK募集!!諭吉3人」と女子高生に対して援助交際を集う内容の書き込みをしました。
実際に援助交際する女子高生と出会う事はありませんでしたが、先日、Aさんは三重県桑名警察署に呼び出されて警察官の取調べを受けました。
出会い系アプリで援助交際を募集することが、出会い系サイト規制法に抵触する事を知ったAさんは不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)
出会い系サイト規制法
出会い系サイト規制法とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律の略称です。
この法律は、出会い系サイト規制法という略称からも分かるように、出会い系サイトの運営者や利用者に様々な規制を行い、出会い系サイトを利用する児童を様々な犯罪から保護する事を目的にしています。
出会い系サイト規制法では
①児童を性交等の相手方となるよう誘引すること
②人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
③対償を供与する事を示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること
④対償を受ける事を示して、人と児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
⑤この他、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人と児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
を禁止誘引行為として定めており、①~④の禁止誘引行為をした者には100万円以下の罰金の罰則を定めています。
出会い系アプリ以外でも禁止誘引行為をすれば出会い系サイト規制法違反で罰せられます!
最近は、出会い系サイトやアプリの規制が厳しくなり、不適切な書き込みは、管理者によってすぐに削除されたり、サイトやアプリの管理者が警察に通報したりするので、違法な書き込みが目立つ出会い系サイトが少なくなってきました。
そのため、インターネットのSNSや掲示板に援助交際を募る書き込みがされているのを目にするようになりました。
出会い系サイトやアプリ以外においても、禁止誘引行為をすれば出会い系サイト規制法に抵触するので注意してください。
まずは弁護士に相談
三重県の刑事事件でお困りの方、出会い系サイトに援助交際を募集する書き込みをしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
ネットカフェの料金を踏み倒し 店員を殴って逃走
店員を殴り、ネットカフェの料金を踏み倒して逃走した桑名市の強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
無職のAはある日、桑名市内のネットカフェで一夜を過ごすことにしましました。
入店した際Aは、深夜パックの料金を前払いして入店したのですが、眠っていたために退店時間を大幅に超過してしまい、数千円の追加料金が発生してしまいました。
店員に起こしてもらえなかったことに怒ったAは店員を殴り、料金を支払わずに店を出て行ってしまいました。
その後、三重県桑名警察署が強盗事件として捜査を開始し、防犯カメラの映像からすぐに特定されてしまったAは三重県桑名警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
2項強盗
刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
強盗罪は上記の様に規定されており、2項では財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事件でAは提供されたサービスの料金の支払いを免れるために店員に暴行を加えているので、2項での強盗罪が成立することになりました。
条文上の「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、これは客観的に判断されます。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されているので、もし起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。
さらに、今回のAが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷罪となってしまう可能性もあります。
強盗致傷罪となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
2項強盗罪のよくある事件の例としては、タクシーでの料金トラブルでタクシー運転手に暴行脅迫を行ってしまい代金を支払わなかった場合が挙げられます。
他にも暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に2項強盗罪が成立した裁判例があります。
一方で2項強盗罪が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂事件や経営者を殺害して経営を継承したという事件があります。
このような場合には2項強盗罪は成立しないと判断されました。
強盗罪の弁護活動
強盗といえば、銀行強盗やコンビニ強盗などお金を奪っていくイメージがあるかもしれませんが、今回の事例の様に料金の踏倒しに関しても強盗罪となってしまうことがあります。
前述したとおり、強盗罪は「5年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が規定されているので、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
弁護士は被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わしたりといった活動で不起訴を目指していきます。
示談交渉は被害者と接触しなければならず、加害者本人が行うのは非常に難しいので、示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
そしてもしも、強盗致傷で起訴されてしまい、裁判員裁判になってしまったとしても刑事事件を専門に扱っている弁護士ならば、しっかりと対応することが可能です。
強盗事件に強い弁護士
料金の踏倒しに関しては強盗罪にはならなくても恐喝罪、詐欺罪となる可能性もありますので、警察が介入していない段階であっても一度専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
三重県桑名市の強盗事件、裁判員裁判対象事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
本日元旦より即日対応可能!!お正月も対応している刑事弁護士
明けましておめでとうございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本年度(令和6年)も1月1日元旦から営業しております。
1月1日~3日に、刑事弁護士がご入用になった際は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)
まで、お気軽にお電話ください。
家族が逮捕された
お正月休み中に、三重県内の警察から「ご家族を逮捕しました。」という電話がかかってきた。
簡単な事件内容を聞くことはできたが、今後の手続きや処分の見通しがつかず不安だ。
このような方は「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスをご利用いただくことで、今後の手続きの流れや、処分の見通しを知ることができます。
また早期に弁護活動をスタートさせることもできますので、早期釈放や刑事処分の軽減させることも可能となります。
勾留通知が届いた
お正月休み中に、裁判所からの勾留通知が届きました。
家族が、〇〇警察署に勾留されているようだが、いまだに弁護士からの連絡は一切ない。
このような方も「初回接見サービス」をご利用ください。
すでに勾留が決定している場合、すでに国選弁護人が選任されている可能性がありますが、まだ選任されていない可能性もあります。
お正月休み中も、刑事手続きは続きますので、勾留されているご家族が、十分な弁護活動を受けられているかどうかを、実際に、逮捕されたご本人に確認し、早急に対応することをお勧めします。
すぐに弁護士に相談したい
昨年末、家族が盗撮事件を起こし在宅捜査を受けています。
年始早々に警察署に呼び出されているのですが、それまでに弁護士に相談したいです。
このような方は「無料法律相談」をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お正月休み中も、刑事事件に関する相談を初回無料で承っております。
お急ぎの相談については、即日対応することも可能ですので是非ご利用ください。
たった今、事件を起こしてしまった
たった今、ひき逃げ事件を起こしてしまった。
飲酒運転が発覚するのが怖くて逃げてしまった・・・
すぐに警察署に出頭しようと思うが一人では不安なので弁護士に付き添ってもらいたい。
このような方も、まずは「無料法律相談/同行サービス」をご利用ください。
ひき逃げ事件のような交通事件に限らず、何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を受け付けております。
弁護士が付き添って警察署に出頭することによって、逮捕の可能性が軽減される事もありますし、何よりも、出頭する方の不安が軽減されるでしょう。
警察署への出頭をお考えの方は、まず弁護士に相談しましょう。
この他にも三重県内で、今すぐ弁護士が必要だ…今すぐ弁護士に相談したい…といった方は、元旦から営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
三重県の方必見!!年末年始営業中の法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年末年始も休まず営業しております。
こんな方は是非ご利用ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年末年始も休まず営業しております。
・ご家族、ご友人が逮捕されてすぐに弁護士を派遣したい方
・年始早々に警察署に出頭して取調べを受ける方
・年末年始にしか休みがなく、普段、弁護士に相談する時間がない方
・また警察沙汰になっていない事件で、早急に被害者との示談を希望の方
などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談・初回接見サービスをご利用ください。
ご家族等が逮捕された方必見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族、ご友人が三重県内の警察署に逮捕された方には、警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しています。
初回接見サービスは電話でご予約いただくことができる非常に便利なサービスで、ご利用後に、弁護活動のご契約をいただければ、最短で弁護活動をスタートすることができます。
初回接見サービスをご利用いただくことによって
・早期釈放
・早期解決
の可能性が高まります。
無料法律相談希望の方必見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、三重県内で刑事事件を起こしてしまった方や、三重県内の警察署、検察庁で取調べを受けている方、既に起訴されて裁判を控えている方など、刑事事件でお困りの方からの相談を初回無料で承っております。
在宅捜査を受けている場合、弁護人を選任できる旨の説明を受ける機会があまりありませんが、在宅捜査を受けている方は、いつでも弁護人を選任することができますので、まずは弁護士を相談することをお勧めします。
・逮捕されるか不安。
・今後の手続きが不安。
・処分の見通しを知りたい。
・弁護士を選任するか悩んでいる。
・被害者との示談を締結させたい。
・警察や検察の取調べに納得ができない。
という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
三重県の刑事事件に強い!!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国12都市に事務所を展開する、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件にお困りの方のお役に立つべく、年中無休で、即日対応をモットーに、刑事事件にお困りの方からのご相談のご予約を24時間体制に受け付けております。
三重県にお住いの方からの刑事事件に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
無人の倉庫に放火 現住建造物等放火罪で逮捕
無人の倉庫に放火したのに現住建造物放火罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
現住建造物等放火罪で逮捕
三重県名張市に住むAさんは、3カ月ほど前まで建設会社に勤めていましたが、会社の代表とトラブルになり、会社をクビになりました。
そのことを恨んでいたAさんは、会社が困らせてやろうと、建築資材を保管している倉庫に、深夜忍び込み灯油をまいて放火したのです。
火は、倉庫に隣接する、作業員が生活している寮に燃え移り、倉庫を全焼し、寮の一部を焼損したところで消し止められ、さいわいにも寮に住んでいる作業員は逃げ出して怪我人はいませんでした。
その後の捜査でAさんの犯行であることが明らかとなり、Aさんは現住建造物等放火罪で三重県名張警察署に逮捕されてしまいました。
非現住建造物等放火と現住建造物等放火罪
現に人のいない、また人が住居として使用していない建物に放火すれば非現住建造物等放火罪です。
逆に、現に人がいる、また人が住居している建物に放火すれば現住建造物等放火罪となります。
Aさんのように、他人が所有する非現住建造物に放火した場合の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」であるのに対して、現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
現住建造物等放火罪で起訴された場合は、その後の刑事裁判は裁判員裁判で行われます。
非現住建造物に放火して現住建造物を焼損
今回の事件のように、非現住建造物に放火して現住建造物を焼損した場合、現住建造物等放火罪に問われる可能性があります。
現住建造物等放火罪に問われるかどうかは、Aさんが放火した際に、隣接する寮に延焼する可能性を認識していたがどうかになるでしょう。
例えAさんが、その認識を否認したとしても、倉庫と寮の距離や、犯行時の気候(風の強さ)などを客観的な状況から未必の故意が認定される可能性があるので注意が必要です。
まずは弁護士に相談
逮捕された罪名と、起訴される際の罪名が同じとは限りません。
逮捕から起訴までの捜査結果次第では、逮捕時よりも重い罪名に変わったり、逆に軽い罪名に変わることはよくあることなので、逮捕された場合は速やかに弁護士を選任して、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、三重県名張市の刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料で承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
家出少女を家に泊めて性交 未成年者誘拐と児童買春
家出少女を家に泊めて性交したとして、未成年者誘拐と児童買春児童買春に問われた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
三重県亀山市に住む会社員のAさん(30歳)は、SNSで知り合った少女(15歳)が家出していることを知り、自宅に泊まりに来るように誘い、誘いにのった少女を自宅に泊めて上げていました。
そんな中、処女と仲良くなったAさんは、「家に泊めて上げているのだからやらしてよ。お小遣い上げるから。」と言い、少女と日常的に性交渉してお小遣いを渡していたのです。
しばらくして少女はAさんが外出中に出て行き、その後何も連絡もなかったのですが、その間に処女は警察に保護されていたらしく、Aさんは、未成年者誘拐と児童買春で三重県亀山警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
未成年者略取・誘拐罪
Aさんが家出少女を自宅に泊めた行為は、は未成年者略取・誘拐罪となります。
(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
欺罔(騙すこと)や誘惑によって、他人を自分や第三者の支配下に置く行為を「誘拐」といいますが、その他の方法(暴行や脅迫を含む)で、他人を自分や第三者の支配下に置いた場合には「略取」といいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
この暴行や脅迫、欺罔や誘惑は、必ずしも誘拐される人に向けられる必要はなく、その監護者に向けられる場合にも「略取」、「誘拐」に当たる可能性があります。
児童買春
児童買春の罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交(淫行)等をすることをいうとされています。
対償とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。
この点、家出中のVさんに対して宿泊場所を提供することも「財産上の利益」といえるでしょう。
未成年者誘拐や児童買春は重たい罪ですから、重罰を免れるためにはまず少女の親と示談交渉を始め、示談を成立させることが賢明です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、示談交渉をご希望の方は是非一度、ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
駐車場に乳児遺体を放置 刑事責任を解説
津市内の駐車場に乳児の遺体放置されていた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
津市内の駐車場で、放置された紙袋の中からポリ袋に包まれた、へその緒が付いた状態の乳児の遺体が発見されました。
司法解剖の結果、遺体は女児で死亡時期は4月頃と推定されていますが、死因は明らかでなく、三重県津警察署は何者かが乳児の遺体を捨てたとみて死体遺棄容疑で捜査しています。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
何罪の成立可能性があるか
本件では、遺棄された乳児にへその尾がついた状態で発見されています。
そのため、乳児が生まれた時既に死亡しており、その遺体を遺棄したか、生まれた時は生きていてが、遺棄された後に死亡してしまったかによって成立する犯罪が変わってきます。
まず、乳児が既に死亡していて、その遺体を遺棄した場合には、死体遺棄罪(刑法190条)が成立する可能性があります。
一方、まだ生存していた乳児を遺棄し死亡させた場合には、遺棄者が「保護責任者」に当たれば保護責任者遺棄致死罪(刑法218条、219条)が、それ以外の者であれば遺棄致死罪が成立する可能性があります。
また、殺意をもって生存していた乳児を遺棄した場合には、殺人罪(刑法199条)が成立する可能性もあります。
死体遺棄罪について
死体遺棄罪は、刑法190条で「死体、遺骨、遺髪、又は棺に納めてある者を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。
本事件において、乳児が生まれた時既に死亡していて、それを遺棄したと仮定した場合、乳児の「死体」を駐車場に「遺棄」したことになるため死体遺棄罪の成立可能性があります。
遺棄等致死罪、殺人罪について
遺棄等致死罪は、刑法219条で「前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、死傷の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
ここでいう前二条として、遺棄罪と保護責任者遺棄罪が定められていますが、両者の区別は遺棄者が要保護者に対して保護する責任のある者に当たるか否かによって区別されます。
本事件においては、乳児が遺棄当時には、まだ生存しており、遺棄行為により死亡したと仮定した場合、乳児は「幼年者」に当たり、遺棄した者が保護責任者(例えば、子に対する親)に当たれば、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。
一方、遺棄者が保護責任者に当たらないとしても、駐車場まで乳児を移動させ放置した場合には、遺棄致死罪の成立も考えられます。
また、保護責任者が殺意をもって乳児を紙袋に入れて駐車場に遺棄したとすれば、殺人罪が成立する可能性もあります。
このコラムをご覧の方で津市内の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が大阪府警に逮捕されてしまった方は、三重県内の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関する無料法律相談や初回接見サービスをお電話で受け付けておりますので、そういったサービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
ご家族が三重県桑名警察署に逮捕されたら
ご家族が三重県桑名警察署に逮捕された場合の、刑事事件専門弁護士の初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇ご家族の逮捕◇
桑名市の建設現場で働いているAさんは、仕事終わりに職場の同僚と一緒に飲みに行きました。
居酒屋で飲んでいた際に、隣のテーブルの大学生の団体客がうるさかったことに腹を立てたAさんは、静かにするように注意したのですが、大学生の一人がAさんに言い返してきたことから、Aさんは、この大学生の顔面を、ビール瓶で殴りました。
同僚にすぐに制止されたのでそれ以上の暴行には及びませんでしたが、大学生はAさんの暴行によって額を裂傷する傷害を負ってしまいました。
そして、その後Aさんは通報で駆け付けた三重県桑名警察署の警察官に、傷害罪で逮捕されてしまいました。
同僚からAさんの逮捕を聞かされた家族は、刑事事件専門弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。(フィクションです。)
◇傷害罪について◇
暴行などにより人の身体を「傷害」した場合、傷害罪が成立します。
ここで言う「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと考えられています。
つまり、殴る蹴るといった行為により受けた外傷のみならず、様々な心身の不調が「傷害」に当たると判断される可能性があるということです。
裁判例では、睡眠薬により長時間の意識障害を生じたケースや、性器を接触させて性病に罹患させたケースで傷害罪の成立を認めたものがあります。
そのため、「傷害」を招く行為についても、典型的な暴行に限定されるわけではありません。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
刑法上、懲役刑の下限は1か月、罰金刑の下限は1万円です。
そのため、裁判において傷害罪で有罪となった場合、刑の選択の幅はかなり広くなることが予想されます。
とはいえ、刑の軽重というのは傷害の程度に大きく左右されるので、全治までどの程度掛かるかで一応の予測を立てることができます。
もし刑の見込みを知りたいとお考えなら、一度お近くの弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事事件の豊富な経験があれば、妥当な範囲の予測を立てたうえで的確な弁護活動の方針を示すことができるでしょう。
◇初回接見サービス◇
逮捕等によって身体拘束を受けている方と、家族など弁護士以外の者が行う面会を一般面会といい、弁護士が行う面会を弁護士接見といいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士の初回接見という有料のサービスを行っています。
このサービスは、既に別の弁護士と接見を行っていたり、別の弁護士に依頼したりしている場合にもご利用いただけます。
初回接見サービスは、被疑者・被告人本人、家族など周囲の者、そして弁護士のいずれにとっても重要な意味があります。
まず、被疑者・被告人は、弁護士から事件の流れや捜査への対処法などを聞くことができます。
多くの方にとって刑事事件というのは馴染みのないものでしょうから、初回接見により安心感を得ることができます。
次に、周囲の者は、弁護士を通して被疑者・被告人と自由に言葉を交わすことができます。
一般面会では立会人の警察官などが話を遮ることもあるので、あらゆることを話せるというのは初回接見の大きなメリットです。
最後に、弁護士は、初回接見で聞いた話に基づき弁護活動の方針を立てることができます。
刑事事件は起こりうることを予測して緻密なスケジュールを立てることが求められるので、弁護士にとってもその出発点となる初回接見はやはり不可欠です。
以上のように初回接見は非常に有益であるため、逮捕の知らせを受けたら一分一秒でも早く弁護士にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、三重県桑名警察署をはじめとした三重県内の警察署に刑事事件専門弁護士を派遣することが可能です。
ご家族、ご友人が、三重県内の警察署に逮捕された方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約や、費用のご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
恐喝罪の成立要件から罰則まで:実例を交えて詳しく解説
恐喝罪は、多くの人が日常的にはあまり遭遇しないが、非常に深刻な犯罪です。
この記事では、恐喝罪が成立する要件、具体的な事例、罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
恐喝罪とは?
恐喝罪は、他人に対して脅迫的な行動を取り、財産を不当に得る行為を指します。
この犯罪は刑法249条に規定されており、日本の法律で厳しく取り締まられています。
恐喝は、暴力団などの反社会勢力と呼ばれるような組織が関与することも多く、かつては社会問題としても注目された時期もあります。
このセクションで、恐喝罪の基本的な定義とその特徴について説明しました。
成立要件の基本
恐喝罪が成立するためには、いくつかの要件が必要です。
まず、意図的な脅迫が行われている必要があります。
これは、「もし何かしなければ何かをする」という形で具体的に表されることが多いです。
次に、その脅迫行為によって財産を不当に得る意図が存在する必要があります。
犯人が脅迫によって何らかの利益を得ることを目的としている場合、この要件は満たされます。
また、被害者が脅迫によって何らかの行動を変更したという事実も重要です。
分かりやすい例を挙げれば、被害者が脅迫に屈してお金を渡した場合、恐喝罪は成立します。
さらに、社会通念上許される範囲を超えた脅迫行為が行われている点も注目されます。
無理な要求や、人々が通常考える範囲を超えた行為が含まれる場合、成立要件が整います。
恐喝の手段について
恐喝罪が成立する際の脅迫手段は多岐にわたります。
一般的に考えられる手段としては、言葉による脅迫が最も多いです。
これには、電話や手紙、最近ではインターネットを使ったものも含まれます。
また、物理的な脅迫もしばしば見られます。
例えば、凶器を持って直接脅す、あるいは身体に触れるなどの行為がこれに該当します。
さらに、状況や環境を利用した脅迫も存在します。
例としては、被害者が財産を渡す以外に選択肢がないような状況を作り出すケースがあります。
珍しいケースとして、他人を利用する形式の脅迫も考えられます。
こちらは、第三者を介して脅迫する行為となり、一般的な恐喝とは一味違った解釈が必要です。
要するに、恐喝の手段は多様であり、具体的な状況に応じてその手法も変わることがあります。
この知識を持つことで、自分自身が何らかの形で恐喝行為に遭遇した際の対処も容易になります。
恐喝罪の実例
恐喝罪の成立要件や手段について理解したところで、具体的な事例を通じてさらに深く知ることが有益です。
最も一般的なケースは、借金の返済を強制する形の恐喝です。
この場合、借金をしている人に対して「返済しなければ身体的な危害を加える」といった脅迫が行われます。
次に、ビジネスの競争相手を脅して市場から撤退させるケースも報告されています。
こちらは、経済的な利益を追求する形の恐喝といえるでしょう。
さらに、最近ではインターネットやSNSを利用して、プライバシーに関する情報を使った恐喝も増えています。
SNSやインターネットが普及した現代では、個人の情報が簡単に流出するリスクが高くなっているため、この手の恐喝事件が増加傾向にあるようです。
被害者の立場から見た対処法
恐喝罪に遭った場合、被害者が取るべき対処法は何か。
その答えを提供するため、以下にいくつかのポイントを詳しく説明します。
まず最初に、警察に相談することが重要です。
多くの被害者は恐怖や恥ずかしさから、事件を公にすることをためらいますが、早期に専門の機関に相談することが解決への第一歩です。
次に、証拠を残すことも大切です。
恐喝行為が行われた状況、それに関わるメッセージや通話履歴、目撃者がいればその証言など、後の法的手続きで役立つ証拠を確保しておく必要があります。
さらに、第三者に相談するメリットもあります。
親しい友人や信頼できる家族、または専門の相談機関など、誰かに話すことで被害状況を客観的に捉えられる場合があります。
また、インターネット上での恐喝に対しては、プロバイダーやSNS運営企業に報告することも有効です。
これによって、加害者のアカウント停止や情報の削除が行われる可能性があります。
加害者が受ける罰則
恐喝罪の成立が確定した場合、加害者はどのような罰則が課されるのでしょうか。
日本の刑法では、恐喝罪に対する罰則が明確に定められています。
起訴されて有罪が確定した場合は、10年以下の懲役の刑が選択されます。
執行猶予が付かなかった場合の刑期は、1年以上10年以下とされていますが、具体的な刑期は裁判での判断によって変動します。
さらに、加害者が組織的な犯罪集団に所属している場合、その罰則はさらに重くなることがあります。
また、犯罪の経緯や動機、被害状況によっては、その他の罪が併せて適用されることもあります。
これは、恐喝だけでなく、他の罪を併せて考慮する必要がある場合があるということです。
一方で、加害者が初犯であり、かつ被害者と和解が成立した場合は、執行猶予が適用される可能性も存在します。
まとめと今後の注意点
本記事では、恐喝罪についてその成立要件から具体的な事例、被害者や加害者が取るべき対応、そして罰則に至るまで幅広く解説してきました。
この知識は、日常生活におけるトラブルや犯罪から自身や他人を守るために非常に有用です。
成立要件の確認
恐喝罪が成立するためには「脅迫」と「不当な利益の獲得」が必要です。
この基本的な要点を理解することが、自身が被害者となるリスクを減らす第一歩となります。
多様な手段
言葉、物理的な脅迫、環境を利用した脅迫など、手段は多岐にわたります。
これを理解しておくことで、多角的な対策が可能となります。
被害者の対処法
警察への相談、証拠の確保、第三者への相談など、対処法も多数存在します。
被害を受けた場合にすぐに動けるよう、これらの方法を頭に入れておくことが重要です。
加害者の罰則
罰則は厳しく、特に組織的な犯罪に関わる場合、その罰はさらに重くなります。
一度恐喝罪で有罪となれば、その後の人生にも多大な影響を及ぼす可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。