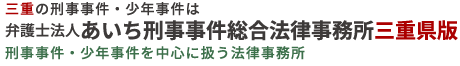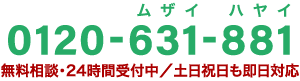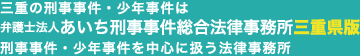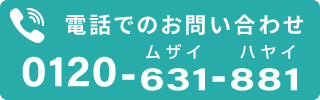Archive for the ‘財産犯事件’ Category
電気窃盗事件で逮捕 不起訴を獲得した解決事例
電気窃盗事件で逮捕 不起訴を獲得した解決事例
電気窃盗事件で逮捕された方の不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
四日市市内でラブホテルを経営しているAさんは、知人と共謀して、電力会社から供給される電気を不正に取得するため電力量計に細工を施し、5年以上に渡って不正に高圧電力の供給を受けていました。
電力量計に細工をしていたことが電力会社に発覚したことから、三重県四日市西警察署に被害届を提出されたAさんは、知人と共に、窃盗罪で逮捕されてしまいました。
逮捕後、20日間もの勾留と共に接見禁止となり弁護士以外との面会ができなかったAさんでしたが、勾留満期と共に不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
窃盗罪
人の物を盗めば窃盗罪となりますが、窃盗罪の被害品は現金や物などのように目に見える物である事がほとんどです。
しかしエネルギーのような無形物であっても、刑法上保護されるような財産的価値のあるもので、かつ人がこれを管理、支配し得るものであれば窃盗罪の客体となります。
つまり電気は窃盗罪の客体となり得、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
共犯者がいる事件では接見禁止になりやすい
裁判官が勾留を決定するのと同時に接見禁止を決定する場合があります。
接見禁止が決定する代表的な事件が、共犯者のいる事件です。
逮捕、勾留されているので共犯者同士が直接接触することは不可能ですが、外部にいる人間を介したり、手紙等を通じて口裏合わせや証拠隠滅を図る可能性が高いとして接見禁止となります。
しかし接見禁止の決定がなされたとして、弁護士の申し立てによって、家族など事件と無関係の人だけでも面会できるようにすることは可能ですので、接見禁止になっている方の面会を希望するのであれば、一度弁護士に相談することをお勧めします。
不起訴
不起訴になれば前科は付きませんが、不起訴になったからといって警察に逮捕された歴が抹消されるわけではないので注意が必要です。
警察に逮捕されたという歴や、警察で採取された被疑者指紋や被疑者写真は、警察庁のデータベースに保存され前歴として登録されてしまいます。
窃盗事件に強い弁護士
今回の事件は電気窃盗という非常に珍しい事件だったため、逮捕までの間に警察も裏付け捜査を徹底しており、当初は不起訴を獲得することが難しいと思われました。
しかしAさんとの接見を繰り返し行い、取調べに対するアドバイスを徹底したことで不起訴を獲得することができました。
このコラムをご覧の方で、窃盗事件に強い弁護士、警察の取調べ対応に対するサポートを必要とされている方がいらっしゃいましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士の無料法律相談を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
窃盗(万引き)事件で逮捕
窃盗(万引き)事件で逮捕
窃盗(万引き)で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
三重県四日市市に住むAさんは、同市内にある大型スーパーマーケットV店で、フライパイン2つ(合計して5000円相当)を会計をせずに店舗外に持ち出しました。
Aさんは駐車場に停めてあった自分の車で逃げようとしましたが、その前で警備員に見つかり、取り押さえられました。
その後、三重県四日市北警察署の警察官が駆け付け、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは「お金を使いたくなかった」と話し、窃盗罪の容疑を認めました。
Aさんは、早く家に帰るためにはどうすればよいのか、窃盗(万引き)事件の取調べではどのようなことが聞かれるのかなどと不安に感じています。
また、Aさんは過去にもV店で万引きをしたことがある(但し、発覚はしなかった)といいます。
(2021年2月22日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪にあたる行為は、他人の財物を「窃取」することです。
この窃盗罪の「窃取」の意味については、他人が事実上支配する財物を、他人の意思に反して、自分の事実上の支配に移転させる行為であると考えられています。
刑事事件例では、Aさんは、V店の商品であるフライパン2点を会計をせずに店舗外に無断で持ち去っています。
このAさんの行為は、V店が事実上支配する財物を、V店の意思に反して、Aさんの事実上の支配に移転させる行為であるので、窃盗罪の「窃取」に当たります。
よって、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
【窃盗(万引き)事件の身柄解放活動について】
窃盗(万引き)事件で逮捕されてしまった場合、刑事弁護士は検察官や裁判官に対して、早急に身体拘束を解くように訴えていくことができます。
具体的な方法としては、検察官による勾留請求・裁判官による勾留決定に対して意見書を提出したり、裁判官による勾留決定に対して不服を申し立てたりすることができます。
窃盗(万引き)事件の身柄解放活動においては、刑事弁護士が早期釈放を求める専門的な書面を作成するほか、身元引受人となってくれる方から被疑者の生活状況や今後の監督方法について話を聞き、それを書面として提出するといった方法が考えられます。
また、被疑者の方に逃亡や証拠隠滅をしないことを誓ってもらい、その旨を書面として提出することも考えられます。
【窃盗(万引き)事件の示談について】
窃盗(万引き)事件が発覚し、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった場合、被疑者の方の身体拘束をすみやかに解くための一つの方法として、示談を締結することが挙げられます。
示談を締結したい場合、被害店舗の担当者の方と刑事弁護士を通して連絡を取り、謝罪や被害弁償をしたいと伝えるといった流れが多いでしょう。
その後、刑事弁護士が被害店舗の担当者の方と直接または電話等により交渉し、示談の具体的な内容について決定していくことになります。
そうした示談交渉を経て、示談交渉に従って被害弁償をする旨や宥恕条項などを記載した示談書を作成し、被害店舗の担当者の方と示談を締結することを目指していきます。
示談が締結できた場合には、刑事弁護士はこの示談書を窃盗(万引き)事件を捜査する検察官に提出することにより、被疑者の方の身体拘束の早期解放を目指すことができます。
【窃盗(万引き)事件の取調べ対応について】
窃盗(万引き)事件では、被疑者の方に逮捕された窃盗(万引き)事件の他に、同じような窃盗(万引き)事件を起こしていないか(余罪がないか)と疑われ、捜査をする検察官や警察官から厳しく追及される可能性があります。
そこで、刑事弁護士は、被疑者の方に黙秘権の保障について分かりやすく説明した上、どのように検察官や警察官の取調べに対して対応していけばよいか、何を話すべきで何を話さないべきかなどを詳しく助言することができます。
窃盗(万引き)事件では、刑事弁護士を選任にすることにより、身柄解放活動や示談交渉、取調べに対する法的助言をすることができると考えられ、刑事事件に強い刑事弁護士を選任することが重要であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗(万引き)事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
盗品等無償譲受け事件で取調べを受けたら
盗品等無償譲受け事件で取調べを受けたら
盗品等無償譲受け事件で取調べを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
三重県伊賀市に住むAさんは、友人のBさんから「高級ブランドバッグが欲しいか」と連絡を受けました。
Bさんはかねてから生活に困窮し、到底高級ブランドバッグなど購入することができない生活状況でありました。
上記事情を知っていたAさんは、「高級ブランドバッグは盗品であるかもしれない。しかし、そんなことは私の知ったことではない。」との意思を抱き、Bさんから高級ブランドバッグを無償で譲り受けました。
その後、Aさんは三重県伊賀警察署の警察官により盗品等無償譲受け罪の容疑で取調べを受けました。
三重県伊賀警察署の警察官によると、実はAさんが譲り受けた高級ブランドバッグは、Bさんが三重県伊賀市のVさんの自宅に侵入し、窃取したものだったといいます。
Aさんは三重県伊賀警察署の警察官からBさんとの関係について詳しく話すよう追及を受けました。
(フィクションです。)
【盗品等無償譲受け罪とは】
刑法256条1項は盗品等無償譲受け罪について以下のように規定しています。
(刑法256条1項)
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
盗品等を無償で譲り受けてしまうと、窃盗罪を含む財産犯罪の被害者の方が、被害品を取り戻す(回復する)ことを困難になってしまいます。
盗品等無償譲受け罪は、窃盗罪を含む財産犯罪の被害者の方が被害品を取り戻す(回復する)ための返還請求権(追求権)を保護するために規定された犯罪であるといえます。
【盗品等無償譲受け罪の成立要件】
盗品等無償譲受け罪が成立するためには、原則として無償譲受けの時点で盗品等であるという事情を知っていること(知情)が必要です。
ただ、この知情は、財物がなんらかの財産犯罪により領得されたものであることを未必的に認識していればよいとされています。
刑事事件例でいえば、高級バッグがなんらかの財産犯罪により領得されたものであることを認識していればよく、必ずしも窃盗罪と罪名を把握している必要はありません。
また、窃盗犯人が誰であるか、被害者の方が誰であるかについては知る必要はないとされています。
刑事事件例のAさんは、「高級ブランドバッグは盗品であるかもしれない。」と認識しています。
そのため、Aさんは、高級ブランドバッグが窃盗罪を含む財産犯罪により領得されたものであることを未必的に認識しているといえると考えられます。
Aさんは、高級ブランドバッグの本来の所有者や窃盗犯人を必ずしも正確に認識しているわけではありませんが、盗品等無償譲受け罪が成立することになります。
そして、Aさんは盗品を「無償で譲り受け」ています。
以上より、Aさんには盗品等無償譲受け罪が成立すると考えられます。
【盗品等無償譲受け罪と共犯、取調べ】
盗品等無償譲受け事件は、その犯罪の性質上、窃盗犯人との共犯関係があったのではないかと疑われる可能性がある刑事事件であるといえます。
たとえば、Aさんが実はBさんの窃盗行為を促したのではないか(Aさんに窃盗罪の教唆犯が成立するのではないか)と疑われる可能性もあるでしょう。
また、Aさんが実はBさんの窃盗行為を手助けしたのではないか(Aさんに窃盗罪の幇助犯が成立するのではないか)と厳しく追及されるおそれも考えられるでしょう。
刑事弁護士としては、刑事事件に関する専門的な知識と経験をもとに、Aさんに、盗品等無償譲受け事件の被疑事実について認めてよい部分・反対に認めてはいけない部分があることなどを詳しく助言した上、警察官や検察官による取調べへの対応方法を助言することができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
盗品等無償譲受け罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も在籍しております。
盗品等無償譲受け事件で取調べを受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
三重県南牟婁郡紀宝町の建造物侵入・窃盗事件で現行犯逮捕
三重県南牟婁郡紀宝町の建造物侵入・窃盗事件で現行犯逮捕
三重県南牟婁郡紀宝町の建造物侵入・窃盗事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、深夜、三重県南牟婁郡紀宝町にある理容室(V店)に正面入り口のガラスを割って侵入し、レジなどで保管されていた現金およそ4万円を盗みました。
三重県紀宝警察署の警察官は、Aさんを建造物侵入罪・窃盗罪の容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんは、建造物侵入罪・窃盗罪の容疑での取調べに対し「生活費としてお金が欲しくてやった」と建造物侵入罪・窃盗罪の容疑を認めています。
Aさんが建造物侵入罪・窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されたと知ったAさんの両親は、三重県の刑事事件に対応している刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年10月12日にSTVニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【建造物侵入罪とは】
「正当な理由がないのに」「人の看守する」「建造物」「に侵入し」「た者」には、建造物侵入罪が成立します(刑法130条)。
建造物侵入罪を犯した者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
建造物侵入罪における「建造物」とは、官公庁や学校、工場、倉庫のような、住居・邸宅以外の建造物をいいます。
住居・邸宅を除くのは、建造物侵入罪とは名称を区別してに、住居侵入罪・邸宅侵入罪が規定されているためです。
刑事事件例におけるV店は建造物侵入罪における「建造物」に該当すると考えられます。
そして、建造物侵入罪が成立するためには、上記建造物侵入罪における「建造物」が「人の看守する」ものである必要があります。
「人の看守する」ものであるとは、監視人を置いたり施錠したりすることによって、事実上管理・支配するための人的・物的設備を施すことをいいます。
刑事事件例におけるV店は、施錠により物的設備が施されていたといえるため、建造物侵入罪における「人の看守する」「建造物」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには建造物侵入罪が成立すると考えられます。
【窃盗罪とは】
「他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪を犯した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
窃盗罪における「窃取」とは、他人の支配する財物を、支配者の意思に反して、自己の支配に移転させる行為を指します。
刑事事件例では、AさんはV店の支配する現金を、V店に意思に反して、Aさんの支配に移転させています。
よって、Aさんの行為は、窃盗罪における「窃盗」に該当すると考えられます。
【器物損壊罪とは】
刑事事件例では、Aさんは建造物侵入罪・窃盗罪で現行犯逮捕されていますが、Aさんには建造物侵入罪・窃盗罪以外に、器物損壊罪も成立すると考えられます。
「他人の物を損壊し」「た者」には、器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪を犯した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を減失させることをいいます。
そして、刑事事件例のガラスを破壊するという行為のように物を物理的に破壊することは、器物損壊罪における「損壊」に該当します。
以上より、Aさんには建造物侵入罪・窃盗罪とは別に、器物損壊罪が成立すると考えられるのです。
【建造物侵入・窃盗・器物損壊事件の刑事弁護活動】
刑事事件例のような建造物侵入・窃盗・器物損壊事件において、刑事弁護士を選任することによる利点のひとつには、建造物侵入・窃盗・器物損壊事件の被害者との示談交渉を円滑に行うことができることにあります。
示談交渉では、Aさんが破壊した正面入り口のガラスの修繕費用を支払ったり、Aさんが窃盗した現金4万円の被害弁償をしたりすることを提案することができると考えられます。
さらに、示談交渉の結果次第では、Aさんの刑事処罰を求めない旨の条項(宥恕条項)を規定した示談を締結することができると考えられます。
示談締結の有無は、検察官や裁判官が建造物侵入・窃盗・器物損壊事件に係る処分を決定する際に重要視される事項です。
そのため、刑事事件に強い刑事弁護士を選任することが大切になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
建造物侵入罪・窃盗罪・器物損壊罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
三重県南牟婁郡の建造物侵入・窃盗事件で現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
詐欺未遂事件の逮捕を相談
詐欺未遂事件の逮捕を相談
詐欺未遂事件の逮捕を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、三重県熊野市に住む男性Vさんに対して電話をかけると、銀行員を名乗り、「Vさんの通帳とキャッシュカードはもう使えなくなったため、新しいものを作り直す必要がある」などと全くの嘘を話し、Vさんから暗証番号を聞き出したうえで通帳とキャッシュカードを騙し取ろうとしました。
しかし、Vさんが電話の内容を不審に思ったことから三重県熊野警察署に通報。
通報を受けて付近を巡回していた三重県熊野警察署の警察官が不審な様子のAさんを発見し、職務質問をしたことからAさんの犯行が発覚し、Aさんは詐欺未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんが詐欺未遂罪の容疑で逮捕されたことを知ると、すぐに弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【詐欺未遂罪とは】
「人を欺いて財物を交付させた者」には、詐欺罪が成立します(刑法246条)。
詐欺罪で有罪となった場合、10年以下の懲役に処せられます。
そして、今回のAさんが詐欺未遂罪の容疑で逮捕されているように、詐欺罪には未遂罪の規定があるため、詐欺罪を完全になし得なかったとしても、詐欺未遂罪で罰せられることとなります(刑法250条)。
詐欺罪は、①詐欺行為者の欺く行為、②被害者の錯誤、③被害者の交付行為、④詐欺行為者の財物の取得という一連の行為により成立します。
そして、詐欺未遂罪は、①欺く行為を行ったものの、結果として財物を取得することができなかった場合に成立します。
詐欺罪・詐欺未遂罪における欺く行為とは、相手が真実を知っていれば財物の交付行為を行わないといえるような重要な事実を偽ることをいいます。
例えば、刑事事件例において、Aさんは「Vさんの通帳とキャッシュカードはもう使えなくなったため、新しいものを作り直す必要がある」とVさんに伝えていますが、これは全くの偽りの情報です。
Vさんが自身の通帳とキャッシュカードが使用できなくなったという話が嘘であると知っていれば、刑事事件例でそうであったように、VさんがAさんに対して通帳とキャッシュカードを交付することはないでしょう。
ですから、Aさんの偽った事実は、相手が真実を知っていれば財物の交付行為を行わないといえるような重要な事実であったといえ、詐欺罪・詐欺未遂罪における「欺く行為」があったと考えられます。
そして、Aさんは詐欺罪・詐欺未遂罪における「欺く行為」を行ったものの、Vさんから通帳とキャッシュカードを受け取る前に、三重県熊野警察署の警察官により逮捕されています。
つまり、Aさんは「欺く行為」をしたものの、結果として財物の交付まで至らなかったということになり、Aさんには詐欺未遂罪が成立すると考えられるのです。
【詐欺未遂罪と執行猶予】
平成30年の検察統計を見てみると、詐欺罪や詐欺未遂罪は他の刑法犯と比較して起訴される確率が高いといえます。
もしAさんが詐欺未遂罪により起訴された場合、無罪判決を獲得する場合を除いて、10年以下の懲役を宣告されることになります。
ただし、裁判所の量刑判断により、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
ある詐欺未遂罪の刑事事件例において、懲役1年6か月・執行猶予3年というような執行猶予付き判決を獲得した事例もあります。
執行猶予付き判決を獲得するためには、執行猶予付き判決を得るに値する事実を裁判所に主張していく必要があります。
例えば、詐欺未遂罪に該当する行為の態様や詐欺未遂事件を起こした動機が悪質でないことや詐欺未遂行為によって発生した被害が甚大とはいえないことなどが挙げられると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
詐欺未遂罪のような財産犯を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある経験豊富な刑事弁護士も多数在籍しております。
三重県熊野市の詐欺未遂事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
強盗傷人罪の少年事件で逮捕されてしまったら
強盗傷人罪の少年事件で逮捕されてしまったら
強盗傷人罪の少年事件で逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(15歳)は、三重県尾鷲市の路上において、歩いて帰宅途中であったVさん(男性)にけがをさせた上で財物を奪取するつもりで、Vさんを羽交い絞めにして倒し、顔を殴るなどして全治約2週間のけがを負わせ、現金約10万円とキャッシュカードなどが入ったショルダーバッグを奪いました。
三重県尾鷲警察署の警察官は、Aさんを強盗傷人罪の容疑を逮捕しました。
強盗傷人罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、今後の手続きがどうなるのか、三重県内にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年10月13日に埼玉新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強盗傷人罪とは】
刑法240条は強盗傷人罪を規定しており、強盗が人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処すとされています。
強盗傷人罪の主体である「強盗」とは、強盗犯人を意味し、既遂・未遂を問わないとされています(最高裁判決昭和23年6月12日)。
そして、強盗傷人罪の主体となる強盗犯人には、刑法236条の強盗罪を犯した者のでなく、事後強盗犯人(刑法238条・刑法243条)や昏睡強盗犯人(刑法239条・243条)が含まれます。
したがって、強盗傷人罪の主体となる「強盗」には広い意味での強盗犯人を意味するので読解にあたり注意が必要です。
ここで、刑法236条をみてみると、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪として、5年以上の有期懲役に処する。」(刑法236条1項)と規定されています。
強盗罪が成立するためには、他人の財物が「暴行又は脅迫」により「強取」される必要があります。
そして、強盗罪における「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りるものである必要があります。
このような「暴行又は脅迫」により被害者の反抗を抑圧して財物を奪取することを強盗罪における「強取」といいます。
刑事事件例において、Aさんは、Vさんを羽交い絞めにして倒し、顔を殴るなどしています。
このAさんの行為は、被害者であるVさんの反抗を抑圧するに足りるものであるといえると考えられます。
よって、Aさんの行為は、強盗罪における「暴行又は脅迫」に該当すると考えられます。
そして、Aさんは、Vさんの反抗を抑圧して、Vさんの現金約10万円とキャッシュカードなどが入ったショルダーバッグを奪取しています。
よって、Aさんは、強盗罪における「強取」をしたと考えられます。
以上より、Aさんには強盗罪が成立する、すなわちAさんは強盗傷人罪の主体となる「強盗」に該当することになると考えられます。
ところで、強盗傷人罪の成立には、強盗傷人罪における「負傷」が強盗による強盗の機会に発生したものである必要があると考えられています(最高裁判決昭和24年5月28日)。
また、強盗傷人罪における「負傷」の程度としても、医師の治療を必要とする程度のものである必要があると考えられています。
刑事事件例では、AさんはVさんを羽交い絞めにして倒し、顔を殴るなどして全治約2週間のけがを負わせています。
そして、このVさんが負った全治2週間のけがは、強盗に機会になされており、負傷の程度としても医師の治療を必要とする程度のものであると考えられます。
以上より、Aさんには強盗傷人罪が成立すると考えられます。
【強盗傷人罪と少年事件】
刑事事件例におけるAさんは、強盗傷人事件を犯した当時15歳です。
そのため、Aさんが少年審判時までに20歳以上に達しない限り、Aさんは少年法における「少年」として扱われることになります(少年法2条1項)。
しかし、強盗傷人事件では、必ずしも少年事件の手続きのみで事件が終局するわけではありません。
というのは、家庭裁判所が「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」は、刑事事件の手続きに戻される可能性があるからです(少年法20条)。
このように少年事件の手続下で処理されていた少年が刑事事件の手続きに戻されることを「逆送」ということがあります。
そして、少年が刑事事件の手続きに戻された場合、捜査段階においては少年鑑別所ではなく拘置所で勾留されたり、刑の執行の段階においては刑務所に収容されたりする可能性があります。
このように、少年にとって、逆送は数多くの大きな不利益があります。
そのため、逆送を回避するような刑事弁護活動(付添人活動)が重要となると考えられます。
例えば、刑事弁護士(付添人)としては、少年事件に関する豊富な経験と知識から、短い審判までの期間で少年の内省を深めるサポートを行ったり、少年の家族と調整し少年をとりまく環境を整えるといった活動が考えられます。
また、家庭裁判所の調査官や裁判官の考える問題点を改善・協議するなどして、少年にとって少年事件の手続き下での処分がふさわしいことを裁判所に対して強く主張することも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗傷人事件を起こした少年のご相談ももちろん受け付けております。
三重県尾鷲市の強盗傷人事件(少年事件)で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
三重県伊勢市の窃盗事件で逮捕されたら
三重県伊勢市の窃盗事件で逮捕されたら
三重県伊勢市の窃盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
三重県伊勢市に住むAさんは、同じく三重県伊勢市内にあるV建設会社の工事現場の敷地内で、V建設会社が管理する電線約50メートル(約2万円相当)を切断して盗み取りました。
V建設会社からの被害届を受けた三重県伊勢警察署の警察官はAさんを窃盗罪の容疑で逮捕しました。
三重県伊勢警察署の警察官によると、三重県伊勢市内では同様の手段による電線の盗難が5件発生しており、三重県伊勢警察署の警察官はAさんに余罪があるとみてAさんを厳しく追及する姿勢を見せています。
窃盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、三重県伊勢市にも対応している刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月29日に佐賀新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
「他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪が成立すると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
窃盗罪における「窃取」とは、他人が事実上支配(占有)する財物を、その事実上の支配(占有)者の意思に反して自己の事実上の支配(占有)に移転させる行為をいいます。
刑事事件例では、AさんはV建設会社が事実上支配(占有)する電線を、事実上の支配(占有)者たるV建設会社の意思に反して、Aさんの事実上の支配(占有)に移転させています。
よって、Aさんの行為は窃盗罪における「窃取」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
【窃盗罪と余罪(詐欺罪・窃盗罪)】
ところで、刑事事件例においては、Aさんは窃盗した電線を中古品買取業者などに買い取ってもらい、その売買代金を領得した可能性が考えられます。
その際、例えばAさんが、電線が盗品であることを隠し、中古品買取業者を騙して電線を買い取らせたというような状況も考えられます。
とすると、Aさんには新たに(余罪として)詐欺罪が成立すると考えられますが、Aさんには窃盗罪のみならず、それに関連する詐欺罪は成立するのでしょうか。
なお、ここでは余罪とは、現に逮捕されている罪以外の犯罪を意味します。
結論から言えば、窃盗罪とは別個に新たに犯罪が成立すると考えられます。
その理由は、端的に言えば、窃盗罪では処罰しきれていない違法性があるからです。
このことをより詳細に検討するには、先に成立する窃盗罪と新たに成立するように思われる詐欺罪はいかなる関係を持つことになるのか、窃盗罪で処罰しきれていない違法性とは何か(反対に窃盗罪で処罰しきれている違法性とは何か)を考える必要があります。
まず、窃盗罪は、一旦犯罪が成立すると以後違法な状態が継続すると考えられています。
これは、例えば窃盗した財物を保持し続ければ違法状態は継続することを想起すれば、「一旦窃盗罪が成立すると以後違法な状態が継続する」と理解できると思います。
そして、窃盗行為に引き続き犯された犯罪行為が、窃盗罪の成立により予定される違法状態の範囲内といえる場合、新たな犯罪行為は既に窃盗罪の成立により評価されていると考えられます(なぜなら、上述のように、窃盗罪は、一旦犯罪が成立すると以後違法な状態が継続することを前提に刑を定めているからです)。
例えば、窃盗行為により領得した財物を損壊する行為は、窃盗罪の成立後も継続する違法状態の範囲内にあると考えられています。
そのため、窃盗行為により領得した財物を損壊しても、器物損壊罪(刑法261条)は成立することなく、窃盗罪のみが成立することになります。
一方、窃盗罪に引き続き犯された犯罪行為が、窃盗罪の成立により予定されている違法状態の範囲外にある場合、換言すれば新たに法益(刑法を定めることにより守られる利益)を侵害する行為であるといえる場合、新たな犯罪行為は窃盗罪の成立により評価されているとは考えられないことになります。
そのため、窃盗罪とは別個に新たに犯罪が成立することになります。
刑事事件例において、Aさんが、電線が盗品であることを隠し、中古品買取業者を騙して電線を買い取らせたというような場合、新たに中古品買取業者の財産(売買代金)が詐取されることになります。
ここに新たな法益の侵害があると考えられ、この法益侵害は窃盗罪では評価され尽くしていないものであるといえます。
よって、Aさんには窃盗罪とは別個に、詐欺罪が成立すると考えられます。
また、刑事事件例において、三重県伊勢市内では同様の手段による電線の盗難が5件発生しています。
Aさんが上記窃盗事件を起こしていた場合、Aさんにはそれぞれの窃盗事件に応じて窃盗罪(余罪)が成立すると考えられます。
以上のようにAさんには詐欺罪や窃盗罪などの余罪が成立する可能性があります。
刑事弁護士としては、三重県伊勢警察署の警察官による厳しい余罪取調べへの対応について専門的な観点から助言したり、窃盗事件(余罪となる窃盗事件も含む)や詐欺事件の被害者との示談を進めたりすることができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
三重県伊勢市の窃盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
三重県鈴鹿市の住居侵入・窃盗事件で逮捕
三重県鈴鹿市の住居侵入・窃盗事件で逮捕
三重県鈴鹿市の住居侵入・窃盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、Bさんと共謀の上、三重県鈴鹿市のVさんの自宅に侵入し、現金200万円が入った金庫や高級車などおよそ4100万円相当の財物を盗みました。
Vさんが三重県鈴鹿警察署に通報した結果、Aさんは三重県鈴鹿警察署の警察官により住居侵入罪・窃盗罪の容疑で逮捕されました。
三重県鈴鹿警察署の警察官は、AさんがVさん以外の人の住居に侵入し財物を盗み取っていないか、共犯者の行方を知らないか厳しく追及しています。
住居侵入罪・窃盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、三重県鈴鹿市の刑事事件に対応している法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月24日に東海新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【住居侵入罪とは】
「正当な理由がないのに、人の住居」「に侵入し」「た者」には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
住居侵入罪における「侵入」とは、居住者の「誰の立入り・滞在を許すか」という意思に反して、住居に立ち入ることをいいます。
刑事事件例において、AさんがVさんの自宅に無断で立ち入ることは、Vさんの「誰の立入り・滞在を許すか」という意思に反するものであったと考えられます。
よって、Aさんの立入りは、住居侵入罪における「侵入」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。
【窃盗罪とは】
「他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪における「窃取」とは、財物の占有(事実上の支配)者の意思に反して、財物を自己の占有(事実上の支配)に移すことをいいます。
刑事事件例において、AさんはVさんの意思に反して、現金200万円が入った金庫や高級車などおよそ4100万円相当の財物を自己の占有(事実上の支配)に移しています。
よって、Aさんの行為は窃盗罪における「窃取」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
【住居侵入罪・窃盗罪と共犯(共同正犯)】
刑事事件例において、Aさんは住居侵入・窃盗行為をBさんと共謀して行っています(共同正犯といいます)。
また、共犯者であるBさんの行方が分からず、当然三重県鈴鹿警察署の警察官によるBさんの住居侵入罪・窃盗罪での逮捕も行われていません。
Aさんを住居侵入罪・窃盗罪の容疑で捜査する検察官は、このような状況においてAさんが釈放されると、AさんがBさんと口裏合わせをする(住居侵入・窃盗事件に関する罪証を隠滅する)おそれがあると考え、Aさんの勾留を請求する可能性があります。
勾留とは、逮捕に引き続きなされ最大で20日(延長された場合)という長期間に及ぶおそれがある身体拘束を意味します。
勾留期間中は仕事や学校には行くことができなくなるため、失業や退学のおそれが生じてしまいます。
刑事弁護士としては、検察官に対してAさんを住居侵入罪・窃盗罪の容疑での勾留を請求しないよう働きかけることができると考えられます。
また、Aさんの住居侵入罪・窃盗罪の容疑での勾留を決定する裁判官に対しても、勾留の決定をしないよう働きかけることができると考えられます。
住居侵入罪・窃盗罪での勾留がなされた場合には、不服申立て(準抗告)をすることもできると考えられます。
【住居侵入罪・窃盗罪と余罪】
逮捕・勾留期間中、Aさんは、三重県鈴鹿警察署の警察官により、Vさん以外の人の住居に侵入し財物を盗み取っていないか、すなわち余罪となる住居侵入罪・窃盗罪を犯していないか厳しい追及を受ける可能性があります。
逮捕・勾留期間中はAさんに取調べを受ける義務(取調受忍義務)が生じるため、長期間に及び厳しい追及がなされる可能性もあります。
被疑者の立場からすれば、肉体的にも精神的にも大きな負担となる可能性があります。
刑事弁護士としては、三重県鈴鹿警察署の警察官や検察官による住居侵入罪・窃盗罪の容疑での取調べに対してどのように応じれば良いのか、法的な観点から詳しく助言することができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入罪・窃盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
三重県鈴鹿市の住居侵入・窃盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
クレプトマニアの万引き事件
クレプトマニアの万引き事件
クレプトマニアの万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
会社員のAさんは、三重県四日市市のコンビニで、お菓子など合わせて3000円相当のものを万引きしました。
しかし、Aさんの万引き現場は警備員に目撃されており、Aさんは通報を受けた三重県四日市北警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんはお金に困っていたわけではなく、欲しいと思ったわけでもないのに万引きをしてしまったと接見にきた弁護士に相談しました。
Aさんは過去にも何度か万引きで捕まっており、弁護士はクレプトマニア(窃盗癖)の可能性もあるのではないかと話しました。
Aさんは、クレプトマニアであるならそれを治して再犯しないようにしたいと考えています。
(※この事例はフィクションです。)
・クレプトマニア(窃盗癖)とは?
クレプトマニア(窃盗癖)とは、窃盗をする衝動が抑えられず、窃盗をすること自体を目的として窃盗を繰り返してしまう精神障害の一つです。
クレプトマニアの特徴としては、窃盗したものを利用する目的(=利益目的)で窃盗をするわけではないこと(例えば、窃盗行為をしてもその盗んだものを使う予定はないなど)、窃盗行為自体に依存しているため窃盗行為の常習性があることなどがあげられます。
また、クレプトマニアと摂食障害などを合わせて発症していることも少なくありません。
・クレプトマニアと万引きの再犯
万引き行為は、当然窃盗罪に当てはまる行為です。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
先ほど触れた通り、クレプトマニアは窃盗行為自体に依存しているために窃盗行為を繰り返してしまう病気ですから、何度も窃盗罪を繰り返し犯してしまい、窃盗罪の再犯として逮捕されてしまうケースが多いです。
万引きなどの窃盗行為を繰り返してしまうと、常習累犯窃盗罪という、窃盗罪よりもさらに重い犯罪が成立する可能性も出てくることにも注意が必要です。
しかし、ただ単に万引きの常習犯であるという点だけに着目されてしまうと、クレプトマニアは治らずにただ重い処罰をくだされてしまい、根本的な解決にはならずにまた再犯を繰り返してしまうというおそれもあります。
しかし、クレプトマニアであるのか、もしもクレプトマニアだとしたらどのような治療をしなければいけないのかは、専門家に診療・治療してもらわなければわからないことです。
それは今回のAさんのように逮捕されたままでは叶わないことですから、まずは弁護士に釈放を求める活動をしてもらい、そこから再犯防止に向けて具体的・効果的な対策を立てていくことが求められるでしょう。
もちろん、クレプトマニアだったからといって万引きなどの窃盗行為が無罪になるわけではありません。
ですが、同じことを繰り返さないための具体的・効果的な再犯防止策を講じていることは、起訴・不起訴の判断や刑罰の重さを決める上でも考慮されます。
まずは弁護士に相談しながら、クレプトマニアの治療を受けるための環境を整えていくことが重要です。
クレプトマニアを治していくために必要なものには、本人の努力はもちろんのこと、ご家族の支えや専門機関での治療などがあげられますが、早期にそれらを受けるには、釈放を実現して在宅捜査で掲示手続きを進めることや、被害者の方への謝罪。示談交渉交渉を速やかに行うことが必要不可欠なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、被疑者の方の事情をじっくりとお聞きし、今後の方針などをご提案します。
万引き事件で逮捕されてお困りの方、万引きを繰り返してしまいもしかしたらクレプトマニアかもしれないとお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
置き引きで不起訴を目指す
置き引き事件で不起訴を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県名張市にあるコンビニに立ち寄り、コンビニ内のトイレを利用したAさんは、トイレの個室内に誰かの置き忘れた財布を発見しました。
Aさんは、その財布を持ったままコンビニを後にし、現場を離れてから財布の中身を確認したところ、現金約3万円、免許証、キャッシュカード1点、クレジットカード1点が入っていたため、現金のみを抜き、他を財布ごと草むらに投げ捨てました。
後日、三重県名張警察署の警察官がAさん宅を訪れ、事件のことで話が聞きたいと言われました。
Aさんは容疑を認めており、警察署で取調べを受けた後に、帰宅しました。
(フィクションです。)
置き引きで問われる罪は?
「置き引き」とは、一般的に、置いてある他人の物を持ち去る行為のことをいいます。
お店のトイレや電車などで誰かがカバンや財布などを置き忘れてしまったものを勝手に持ち去ってしまうのが典型例です。
置き引き行為は、被害者(持ち去られた物の所有者)の占有が認定できるかどうかで窃盗罪又は遺失物横領罪となります。
窃盗罪は、「他人の財物を窃取する」罪です。
ここで言う「他人の財物」とは、「他人の占有する財物」のことを意味します。
窃盗罪における「占有」は、人が物を実力的に支配する関係のことを指し、物を握持することがその典型例ですが、それ以外にも、物に対する「事実上の支配」があれば、刑法で保護する必要が高く、窃盗における「占有」が認められます。
刑法で保護される必要がある「事実上の支配」とは、物を客観的に支配している場合はもちろんのこと、物の支配を取り戻そうと思えばいつでも取り戻せる状態も含みます。
そして、物を取り戻そうと思えばいつでも取り戻せる状態であるか否かについては、支配の事実や占有の意思という2つの要素から判断されます。
支配の事実については、持ち主が物を置き忘れてから気が付くまでの時間的、場所的接近性などが重要な要素となります。
また、占有の意思については、持ち主が物の存在していた場所をどの程度認識していたかなどについて検討されます。
通常、バッグや財布を置き忘れたようなケースでは、持ち主がすぐに気が付くことが多く、当該バッグや財布は、「他人の占有する財物」と言え、窃盗となることが多いです。
しかし、物に持ち主の占有が認められるか否かが微妙なケースでは、窃盗ではなく占有離脱物横領罪が成立する余地があるでしょう。
置き引き事件で不起訴を目指す場合
置き引きは、窃盗事犯の中でも比較的軽微な部類に属するため、被害額が少なく、被害が既に回復されており、再犯のおそれもない場合には、微罪処分となることがあります。
しかし、被害額がある程度大きく、被害回復ができていない場合には、事件は警察から検察に送られ、検察官が最終的な処分を決定します。
上記事例では、被害額から言って、検察に送致されるものと考えられます。
ですので、検察官が最終的な処分を決定するときに、不起訴処分となるよう被害の回復と再犯防止措置を講じておくことが必要です。
置き引きは財産犯であるため、被害の回復、つまり、被害者への被害弁償を行うことが重要です。
通常、被害者への被害弁償や示談交渉は、弁護士を介して行います。
捜査機関は、加害者が被害者に供述の変更を求めるなどの罪証隠滅を行うおそれがあると認め被害者の連絡先を加害者に教えることはあまりありませんし、被害者も加害者に対してよい感情はありませんので、自分の連絡先を教えたがらないことがあります。
ですが、被害者も盗まれた物の弁償を希望することがほとんどであり、弁護士を介して被害弁償や示談交渉を申し込んだ場合には、話し合いに応じてもらえることが多いです。
無論、処罰感情が高い方は、被害弁償を受けないと話し合いも断る方もいらっしゃいますので、一概に全ての被害者の方が話し合いに応じられるとは限りません。
弁護士は、被害者の方の気持ちを考慮しつつ、被害弁償や示談に応じることのメリット・デメリットを丁寧に説明し、粘り強く話し合いを続け、当事者双方が納得することができる内容となるよう尽力します。
検察官が終局処分を下すまでに、被害弁償や示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性を高めることができます。
ですので、早期に弁護士に相談し、被害の回復に努めることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件で対応にお困りであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。