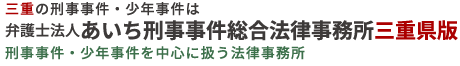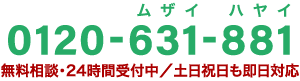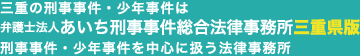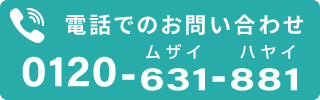Author Archive
三重県鳥羽市の特別公務員暴行陵虐事件で書類送検
三重県鳥羽市の特別公務員暴行陵虐事件で書類送検
三重県鳥羽市の特別公務員暴行陵虐事件で書類送検された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、三重県鳥羽警察署の警察官であったところ、三重県鳥羽市内を巡回中、Vさんに職務質問をした上、DNA採取が必要だと偽り、Vさんの口の中に綿棒をこすり付けたり指でVさんの口の中を触ったりしました。
三重県鳥羽警察署は、Aさんを懲戒免職した上、特別公務員暴行陵虐罪の容疑で書類送検(検察官送致)しました。
Aさんは、特別公務員暴行陵虐罪の容疑を求めており、「女性の口の中を見たい、触りたいという性癖から犯行に及んだ。」と供述しています。
Aさんは、刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年1月31日に千葉日報に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【特別公務員暴行陵虐罪とは】
「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたとき」には特別公務員暴行陵虐罪が成立します(刑法195条)。
特別公務員暴行陵虐罪の法律に定められた刑(法定刑)は、7年以下の懲役です。
まず、刑事事件例におけるAさんは三重県鳥羽警察署の警察官であり、特別公務員暴行陵虐罪の主体に当たる「裁判、検察若しくは検察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者」に該当します。
次に、特別公務員暴行陵虐罪における「職務を行うに当たり」とは、「職務を行う機会に」ということを意味します。
そして、特別公務員暴行陵虐罪に該当する行為は「職務を行う機会に」されれば、その目的が何であるかは問わず(すなわち職務遂行の達成を目的としてされることを必要とせず)、個人的欲望を満たす目的で行われた場合であっても、特別公務員暴行陵虐罪における「職務を行うに当たり」に該当すると考えられます。
刑事事件例における職務質問は、行政警察としての「職務を行う機会」に該当し、特別公務員暴行陵虐罪における「職務を行うに当たり」という要件を満たすと考えられます。
また、特別公務員暴行陵虐罪の客体に当たる「被告人、被疑者その他の者」には、刑法195条の条文に例示された被告人・被疑者のみならず、行政警察作用の対象となる者も含まれると考えられています。
刑事事件例における職務質問を受けたVさんは、行政警察の対象となる者として、特別公務員暴行陵虐罪における「被告人、被疑者その他の者」に該当すると考えられます。
さらに、特別公務員暴行陵虐罪における「暴行」とは身体に対する不法な有形力の行使を、「陵辱」とは被害者をはずかしめる行為など精神的な苦痛を与える行為を、「加虐」とは「暴行」以外の方法で肉体的な苦痛を与える行為を指します。
すなわち、特別公務員暴行陵虐罪における「陵辱」・「加虐」とは、「暴行」以外の方法で精神的又は身体的に苦痛を与える行為を指すといえます。
刑事事件例において、AさんはVさんの口の中に綿棒をこすり付けたり指で口内を触ったりしているところ、この行為ははVさんに精神的な苦痛を与える行為であるとして特別公務員暴行陵虐罪における「陵辱」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには特別公務員暴行陵虐罪が成立すると考えられます。
【特別公務員暴行陵虐罪と示談】
Aさんは現在、特別公務員暴行陵虐罪の容疑で書類送検(検察官送致)されていますが、Aさんを特別公務員暴行陵虐罪の容疑で捜査する検察官は、Aさんを特別公務員暴行陵虐罪で起訴する可能性があります。
刑事弁護士としては、特別公務員暴行陵虐事件の被害者であるVさんと示談交渉をし、示談交渉の結果次第では、Aさんを特別公務員暴行陵虐罪の容疑で捜査する検察官に対して、寛大な処分をするよう求めることができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
三重県鳥羽市の特別公務員暴行陵虐事件で書類送検された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
三重県伊勢市の窃盗事件で逮捕されたら
三重県伊勢市の窃盗事件で逮捕されたら
三重県伊勢市の窃盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
三重県伊勢市に住むAさんは、同じく三重県伊勢市内にあるV建設会社の工事現場の敷地内で、V建設会社が管理する電線約50メートル(約2万円相当)を切断して盗み取りました。
V建設会社からの被害届を受けた三重県伊勢警察署の警察官はAさんを窃盗罪の容疑で逮捕しました。
三重県伊勢警察署の警察官によると、三重県伊勢市内では同様の手段による電線の盗難が5件発生しており、三重県伊勢警察署の警察官はAさんに余罪があるとみてAさんを厳しく追及する姿勢を見せています。
窃盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、三重県伊勢市にも対応している刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月29日に佐賀新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
「他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪が成立すると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
窃盗罪における「窃取」とは、他人が事実上支配(占有)する財物を、その事実上の支配(占有)者の意思に反して自己の事実上の支配(占有)に移転させる行為をいいます。
刑事事件例では、AさんはV建設会社が事実上支配(占有)する電線を、事実上の支配(占有)者たるV建設会社の意思に反して、Aさんの事実上の支配(占有)に移転させています。
よって、Aさんの行為は窃盗罪における「窃取」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
【窃盗罪と余罪(詐欺罪・窃盗罪)】
ところで、刑事事件例においては、Aさんは窃盗した電線を中古品買取業者などに買い取ってもらい、その売買代金を領得した可能性が考えられます。
その際、例えばAさんが、電線が盗品であることを隠し、中古品買取業者を騙して電線を買い取らせたというような状況も考えられます。
とすると、Aさんには新たに(余罪として)詐欺罪が成立すると考えられますが、Aさんには窃盗罪のみならず、それに関連する詐欺罪は成立するのでしょうか。
なお、ここでは余罪とは、現に逮捕されている罪以外の犯罪を意味します。
結論から言えば、窃盗罪とは別個に新たに犯罪が成立すると考えられます。
その理由は、端的に言えば、窃盗罪では処罰しきれていない違法性があるからです。
このことをより詳細に検討するには、先に成立する窃盗罪と新たに成立するように思われる詐欺罪はいかなる関係を持つことになるのか、窃盗罪で処罰しきれていない違法性とは何か(反対に窃盗罪で処罰しきれている違法性とは何か)を考える必要があります。
まず、窃盗罪は、一旦犯罪が成立すると以後違法な状態が継続すると考えられています。
これは、例えば窃盗した財物を保持し続ければ違法状態は継続することを想起すれば、「一旦窃盗罪が成立すると以後違法な状態が継続する」と理解できると思います。
そして、窃盗行為に引き続き犯された犯罪行為が、窃盗罪の成立により予定される違法状態の範囲内といえる場合、新たな犯罪行為は既に窃盗罪の成立により評価されていると考えられます(なぜなら、上述のように、窃盗罪は、一旦犯罪が成立すると以後違法な状態が継続することを前提に刑を定めているからです)。
例えば、窃盗行為により領得した財物を損壊する行為は、窃盗罪の成立後も継続する違法状態の範囲内にあると考えられています。
そのため、窃盗行為により領得した財物を損壊しても、器物損壊罪(刑法261条)は成立することなく、窃盗罪のみが成立することになります。
一方、窃盗罪に引き続き犯された犯罪行為が、窃盗罪の成立により予定されている違法状態の範囲外にある場合、換言すれば新たに法益(刑法を定めることにより守られる利益)を侵害する行為であるといえる場合、新たな犯罪行為は窃盗罪の成立により評価されているとは考えられないことになります。
そのため、窃盗罪とは別個に新たに犯罪が成立することになります。
刑事事件例において、Aさんが、電線が盗品であることを隠し、中古品買取業者を騙して電線を買い取らせたというような場合、新たに中古品買取業者の財産(売買代金)が詐取されることになります。
ここに新たな法益の侵害があると考えられ、この法益侵害は窃盗罪では評価され尽くしていないものであるといえます。
よって、Aさんには窃盗罪とは別個に、詐欺罪が成立すると考えられます。
また、刑事事件例において、三重県伊勢市内では同様の手段による電線の盗難が5件発生しています。
Aさんが上記窃盗事件を起こしていた場合、Aさんにはそれぞれの窃盗事件に応じて窃盗罪(余罪)が成立すると考えられます。
以上のようにAさんには詐欺罪や窃盗罪などの余罪が成立する可能性があります。
刑事弁護士としては、三重県伊勢警察署の警察官による厳しい余罪取調べへの対応について専門的な観点から助言したり、窃盗事件(余罪となる窃盗事件も含む)や詐欺事件の被害者との示談を進めたりすることができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
三重県伊勢市の窃盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
重過失致死事件で書類送検された
重過失致死事件で書類送検された
重過失致死事件で書類送検された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
三重県多気郡大台町に住むAさんは、息子であるVさん(2歳)を自宅駐車場に停めた車の中に置き忘れ、約10時間放置し、熱中症により死亡させました。
その後、Aさんは、三重県大台警察署の警察官により、重過失致死罪の容疑で取調べを受けました。
重過失致死事件発生当時、Aさんは、仕事が忙しかったあまり、Vさんを車内に置き忘れたことに気が付かなかったといいます。
その後、Aさんは重過失致死罪の容疑で書類送検されました。
(2021年1月19日に共同通信に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【重過失致死罪とは】
刑法211条2項は、重過失致死罪を規定しています。
この刑法211条2項の重過失致死罪は、刑法211条1項の業務上過失致死傷罪の規定を一部引用しています。
刑法211条1項
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
刑法211条2項
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
すなわち、重大な過失により人を死傷させた者には重過失致死罪が成立し、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されることになります。
刑法211条2項の重過失致死罪の「重過失」とは、注意義務を著しく怠って死亡結果を発生させることをいいます。
具体的には、重過失致死罪の「重過失」とは、容易に死亡結果の発生を予見することができ、かつ容易に死亡結果の発生を回避し得るのに、その注意義務(結果予見義務・結果回避義務)を怠って死亡結果を発生させた場合をいいます。
刑事事件例においては、AさんはVさん(2歳)を自宅駐車場に停めた車の中に置き忘れ、約10時間放置し、熱中署により死亡させています。
ここで、2歳の子ども(Vさん)を約10時間に車の中に放置した場合、熱中症等により死亡が発生するおそれがあることは、容易に予見できたと考えられます。
また、Vさんを車から連れ出せば容易に死亡結果の発生を回避し得たと考えられます。
それにも関わらず、Aさんはこれらの注意を怠ってVさんを死亡させています。
よって、Aさんには重過失致死罪の「重過失」があり、この重過失によってVさんを「死傷させた」といえると考えられ、Aさんには重過失致死罪が成立すると判断されたのでしょう。
【重過失致死事件と書類送検】
刑事事件例では、Aさんは三重県大台警察署の警察官により重過失致死罪の容疑で取調べを受けました。
その後、Aさんは重過失致死罪の容疑で書類送検されました。
書類送検とは、刑事訴訟法における用語では「送致」といいます。
刑事訴訟法246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
書類送検(送致)とは、事件自体を検察官に引き継ぐことをいいます。
具体的には、書類送検(送致)により事件の記録や証拠品が検察官に引き継がれることになります。
そして、事件を引き継いだ検察官は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」(刑事訴訟法248条)などを考慮して起訴するかどうかを決定します。
この際、被疑者の方を検察庁まで呼び出し、事件の経緯などの取調べを受けることになります。
刑事事件例でも同様に、重過失致死事件の書類送検(送致)がなされた後、Aさんは検察官による呼出し・取調べを受けることになります。
取調べでは、重過失致死事件を起こした経緯、重過失致死事件を起こした当時の心情、今後の更生についてなど様々な事柄が聞かれる可能性があります。
刑事弁護士としては、法律の専門的な見地と様々な刑事事件を取り扱った豊富な経験をもとに、このような重過失致死事件に関する取調べに対してどのように対応すればよいか助言することができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
重過失致死事件で書類送検された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
過失運転致傷事件で執行猶予を得たい
過失運転致傷事件で執行猶予を得たい
過失運転致傷事件で執行猶予を得たい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(25歳)は、三重県松阪市内を自動車で走行してましたが、考え事をしていたり仕事の疲れが溜まっていたりしたため運転に注意することができていませんでした。
そして、信号が赤になったことに気が付かず、そのまま交差点に進入し、Vさん(80歳)をはねました。
Vさんは病院に運ばれ、死亡するには至らなかったものの、意識不明の重体となりました。
Aさんは、三重県松阪警察署の警察官により過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは何とか刑務所に行かずに済むようにしてほしいと考えています。
(2021年1月29日に九州朝日放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【過失運転致傷罪とは】
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条に規定されています。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致傷罪の「運転上必要な注意」とは、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において、自動車を動かす上で必要な注意義務をいいます。
ここで、道路交通法では自動車の運転者が守るべき義務が定められています。
過失運転致傷罪の「運転上必要な注意」を怠ったか否かは、この道路交通法の規定を参酌して判断されます。
ただし、道路交通法の規定を遵守していなかったからといって直ちに過失運転致傷罪の「運転上必要な注意」を怠ったと認められるわけではありません。
刑事事件例では、Aさんは、信号が赤になったことに気が付かず、そのまま交差点に進入し、Vさんをはねています。
周知のとおり、自動車の運転者は安全確認をしながら走行する義務を負います(道路交通法70条参照)。
それにもかかわらずAさんは漫然運転をしており、Aさんは過失運転致傷罪の「運転上必要な注意」としての安全運転義務を怠ったと認められることになります。
そして、Vさんを意識不明の重体となっており、ここに過失運転致傷罪の傷害が生じていると考えられます。
以上より、Vさんは過失運転致傷罪の容疑で逮捕されることになったのだと考えられます。
【過失運転致傷事件で逮捕された後の流れ】
過失運転致傷罪の容疑で逮捕された場合、検察官の処分としては、Aさんには①不起訴、②略式起訴、③正式起訴のいずれかがなされます。
このうちいずれの処分が下されるかは、過失運転致傷事件によって生じた被害の程度、犯罪行為の悪質性、注意義務違反の態様、示談の有無など、様々な事情によって決定されます。
特に、刑事事件例では、過失運転致傷事件の被害者の方が意識不明の重体となっており、過失運転致傷事件によって生じた結果としては大きいと考えられ、Aさんが正式起訴をされる可能性もあります。
【過失運転致傷事件で執行猶予を得るには】
もしAさんが過失運転致傷事件で正式起訴されてしまった場合、執行猶予判決を得るためには、裁判において、真摯に謝罪していることや二度と犯罪を犯さないこと、正式な被害弁償をしたことなどを裁判所に示していくことが重要です。
そこで、刑事弁護士としては、ご家族などの情状証人への尋問、過失運転致傷事件の被告人の方への質問などを通して、これらのことを裁判所に示していくことができると考えられます。
例えば、情状証人としてAさんのご両親に裁判所に出廷してもらい、被告人の方の性格や生活状況、今後の監督方法などについて話してもらうことができます。
また、示談が成立していれば、過失運転致傷事件の被告人の方には真摯に謝罪しており、相当な被害弁償をしたことを話してもらうことができます。
刑事弁護士は、情状証人の方・被告人の方が不安なく裁判所において話ができるよう、事前に入念に打ち合わせをしたり、助言をしたりすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過失運転致傷事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
侮辱事件で告訴を取り消してほしい
侮辱事件で告訴を取り消してほしい
侮辱事件で告訴を取り消してほしい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、当時中学生だった三重県津市に住んでいるVさんが平和を訴えるイベントに参加した旨を伝える記事を見たことをきっかけに、Aさん自身が作成する外国人の排除を求めるブログに、Vさんの出自などを誹謗中傷する文章を投稿しました。
その後、Vさんは通信業者に発信者情報の開示を請求し、開示されたAさんの氏名をもとに、Aさんを侮辱罪で三重県津南警察署に告訴しました。
その後、Aさんは三重県津南警察署の警察官による取調べを受けました。
Aさんは何とか刑事裁判を逃れられるようにしてほしいと考えています。
(2019年1月16日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【侮辱罪とは】
近年、インターネット上での誹謗中傷が大きな社会問題となっています。
刑事事件例におけるAさんの投稿もその一つといえます。
以下では、インターネット上での誹謗中傷と刑事事件の関係を見ていきます。
刑法231条は、侮辱罪を規定しています。
侮辱罪の具体的な内容(要件)は以下の通りです。
刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
侮辱罪は人を「公然と」「侮辱」した場合に成立する犯罪です。
侮辱罪の「公然と」(公然性)とは、摘示された事実を不特定または多数人が認識しうる状態をいうと考えられています。
そして、侮辱罪の「公然と」(公然性)における不特定とは、相手方が限定されていないことをいいます。
また、侮辱罪の「公然と」(公然性)における多数人とは、相手方が特定されているがその数が多数であることをいいます。
刑事事件例では、AさんのVさんを誹謗中傷した投稿(ブログ)は、不特定または多数人が閲覧することができたものであったと考えられます。
よって、Aさんの投稿は、侮辱罪の「公然と」(公然性)の要件を満たすと考えられます。
また、侮辱罪の「侮辱」とは、人に対する侮辱的価値判断(軽蔑)の表示をいうと考えられています。
そして、侮辱罪の「侮辱」は、具体的な事実の摘示することなく行われる必要があります。
例えば、「バカ」「アホ」といった発言には具体的な事実の摘示が含まれていません。
したがって、この発言は侮辱罪の「侮辱」に該当しうることになります。
これに対して、例えば、「あいつは隣の奥さんと浮気していた」という発言には具体的な事実の摘示がされています。
したがって、この発言については侮辱罪ではなく、名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立しうることになります。
刑事事件例では、AさんはVさんの出自について誹謗中傷する投稿をしています。
そして、この誹謗中傷は、具体的な事実を摘示することなく、Vさんに対する侮辱的価値判断(軽蔑)の表示であったと考えられます。
よって、Aさんの投稿は侮辱罪の「侮辱」に該当すると考えられます。
【侮辱罪と親告罪、告訴取消し】
侮辱罪は親告罪であるとされています。
侮辱罪が親告罪であることは刑法232条に規定されています。
刑法232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
親告罪とは、被害者の方(厳密には、被害者の方に加えて法定の者を含みます)による告訴(処罰を求める意思表示)がなければ刑事裁判に提訴(起訴)することができない犯罪のことをいいます。
刑事事件例では、侮辱罪は親告罪であるため、Vさんによる告訴がなければ刑事裁判に提訴(起訴)することができません。
ですから、侮辱罪を含む親告罪についての刑事弁護士の主たる弁護活動の1つとしては、被害者の方と示談をして告訴を取り消してもらえないか交渉することが考えられます。
親告罪であるということは、告訴の取消し(刑事訴訟法237条1項)をしてもらうことができれば、Aさんは刑事裁判にかけられることがなくなるためです。
侮辱罪のような親告罪を犯した場合には、刑事事件に強い弁護士を選任し、いち早く示談交渉を開始することが重要です。
侮辱罪は、厳罰化の方針が取られている犯罪であり、インターネットやSNSが発達した現在では、注目の集まる犯罪の1つです。
その一方、どういったことが侮辱罪にあたるのか、どのような犯罪なのかご存知でない方も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
侮辱罪のような親告罪を犯した方の刑事弁護活動を行い、告訴を取り消してもらう内容の示談を締結したことのある刑事弁護士も在籍しております。
侮辱事件で告訴を取り消してほしいとお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
強制わいせつ事件の示談交渉
強制わいせつ事件の示談交渉
強制わいせつ事件の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、午後8時頃、三重県津市の路上において、スマホを操作しながら歩いていた20代の女子学生(Vさん)に後ろから抱き付き、上半身を触りました。
Vさんがバランスを崩して路上に倒れ悲鳴を上げたため、Aさんは走って逃走しました。
その後、Vさんが近くの交番に駆け込んだため、強制わいせつ事件が発覚しました。
三重県津警察署の警察官は、Aさんを強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、三重県の刑事事件にも対応している法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年10月3日に北海道ニュースUHBに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
刑法176条は「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」とし、強制わいせつ罪を規定しています。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」は、性欲を刺激し、興奮又は満足させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうと考えれています。
そして、刑事事件例においてAさんが行ったVさんの背後から抱き付き、上半身を触る行為は、争いなく、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当すると考えられます。
また、強制わいせつ罪の成立には、「暴行又は脅迫」を手段として、上記わいせつな行為を行うことが必要です。
この強制わいせつ罪における「暴行」とは、身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
強制わいせつ罪における「暴行」には、殴る・蹴る等の行為が含まれるのは当然ですが、不意に股間に手を差し入れる行為のように、暴行自体がわいせつな行為に該当する場合であってもよいと考えられています。
刑事事件例において、上述の通り、AさんはVさんの背後から抱き付き、上半身を触っています。
このAさんの行為は、上述の通り強制わいせつ罪における「わいせつな行為」にも該当しますが、強制わいせつ罪における「暴行」にも該当すると考えられます。
以上より、Aさんには強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
【強制わいせつ罪と示談】
強制わいせつ事件のように被害者の方がおり、被害者の方の処罰感情が加害者(Aさん)に対する処分にあたり重要視される刑事事件の場合、被害者の方と示談をすることが重要となります。
被害者の方との示談交渉の結果次第では、仮にAさんが強制わいせつ罪で刑事裁判に起訴されてしまったとしても、執行猶予付き判決を獲得することができる可能性があります。
示談締結によって不起訴処分となることもありますから、示談の有無、示談交渉の有無は事件の処分に大きく影響するといえます。
また、被害者の方との示談交渉が円滑に行われ、Aさんが強制わいせつ罪で刑事裁判に起訴されてしまう前の身体拘束期間中に示談締結をすることができた場合、示談の存在を考慮し、早期にAさんに対する身体拘束が解かれる可能性もあります。
先ほど触れたような事件の結果自体だけでなく、逮捕・勾留からの釈放という面でも、示談交渉は重要な活動の1つなのです。
このような大きなメリットが得られる示談交渉を円滑に進めるためには、刑事事件に強い刑事弁護士を選ぶことが重要であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ罪を犯した方の刑事弁護活動、示談交渉を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
三重県津市の強制わいせつ事件で示談を目指す場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
三重県鈴鹿市の住居侵入・窃盗事件で逮捕
三重県鈴鹿市の住居侵入・窃盗事件で逮捕
三重県鈴鹿市の住居侵入・窃盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、Bさんと共謀の上、三重県鈴鹿市のVさんの自宅に侵入し、現金200万円が入った金庫や高級車などおよそ4100万円相当の財物を盗みました。
Vさんが三重県鈴鹿警察署に通報した結果、Aさんは三重県鈴鹿警察署の警察官により住居侵入罪・窃盗罪の容疑で逮捕されました。
三重県鈴鹿警察署の警察官は、AさんがVさん以外の人の住居に侵入し財物を盗み取っていないか、共犯者の行方を知らないか厳しく追及しています。
住居侵入罪・窃盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、三重県鈴鹿市の刑事事件に対応している法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月24日に東海新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【住居侵入罪とは】
「正当な理由がないのに、人の住居」「に侵入し」「た者」には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
住居侵入罪における「侵入」とは、居住者の「誰の立入り・滞在を許すか」という意思に反して、住居に立ち入ることをいいます。
刑事事件例において、AさんがVさんの自宅に無断で立ち入ることは、Vさんの「誰の立入り・滞在を許すか」という意思に反するものであったと考えられます。
よって、Aさんの立入りは、住居侵入罪における「侵入」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。
【窃盗罪とは】
「他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪における「窃取」とは、財物の占有(事実上の支配)者の意思に反して、財物を自己の占有(事実上の支配)に移すことをいいます。
刑事事件例において、AさんはVさんの意思に反して、現金200万円が入った金庫や高級車などおよそ4100万円相当の財物を自己の占有(事実上の支配)に移しています。
よって、Aさんの行為は窃盗罪における「窃取」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
【住居侵入罪・窃盗罪と共犯(共同正犯)】
刑事事件例において、Aさんは住居侵入・窃盗行為をBさんと共謀して行っています(共同正犯といいます)。
また、共犯者であるBさんの行方が分からず、当然三重県鈴鹿警察署の警察官によるBさんの住居侵入罪・窃盗罪での逮捕も行われていません。
Aさんを住居侵入罪・窃盗罪の容疑で捜査する検察官は、このような状況においてAさんが釈放されると、AさんがBさんと口裏合わせをする(住居侵入・窃盗事件に関する罪証を隠滅する)おそれがあると考え、Aさんの勾留を請求する可能性があります。
勾留とは、逮捕に引き続きなされ最大で20日(延長された場合)という長期間に及ぶおそれがある身体拘束を意味します。
勾留期間中は仕事や学校には行くことができなくなるため、失業や退学のおそれが生じてしまいます。
刑事弁護士としては、検察官に対してAさんを住居侵入罪・窃盗罪の容疑での勾留を請求しないよう働きかけることができると考えられます。
また、Aさんの住居侵入罪・窃盗罪の容疑での勾留を決定する裁判官に対しても、勾留の決定をしないよう働きかけることができると考えられます。
住居侵入罪・窃盗罪での勾留がなされた場合には、不服申立て(準抗告)をすることもできると考えられます。
【住居侵入罪・窃盗罪と余罪】
逮捕・勾留期間中、Aさんは、三重県鈴鹿警察署の警察官により、Vさん以外の人の住居に侵入し財物を盗み取っていないか、すなわち余罪となる住居侵入罪・窃盗罪を犯していないか厳しい追及を受ける可能性があります。
逮捕・勾留期間中はAさんに取調べを受ける義務(取調受忍義務)が生じるため、長期間に及び厳しい追及がなされる可能性もあります。
被疑者の立場からすれば、肉体的にも精神的にも大きな負担となる可能性があります。
刑事弁護士としては、三重県鈴鹿警察署の警察官や検察官による住居侵入罪・窃盗罪の容疑での取調べに対してどのように応じれば良いのか、法的な観点から詳しく助言することができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入罪・窃盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
三重県鈴鹿市の住居侵入・窃盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
三重県亀山市の器物損壊事件で示談を目指す
三重県亀山市の器物損壊事件で示談を目指す
三重県亀山市の器物損壊事件で示談を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、三重県亀山市において、軽乗用車で道路を走行中、前を走っていたVさんの車がゆっくり走っていたことに腹を立て、信号で乗用車が止まった際にVさんと口論をした後、ハンマーでVさんの乗用車のフロントガラスなどを叩き割りました。
Aさんは、三重県亀山警察署の警察官により、器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、三重県亀山警察署の警察官による器物損壊罪の容疑での取調べに対し、器物損壊罪の容疑を認めているということです。
Aさんが器物損壊罪の容疑で逮捕されたと聞いたAさんの妻は、三重県内にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年10月19日にCBCNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【器物損壊罪とは】
刑法261条は、以下のように規定しています。
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する(刑法261条)。
また、刑法264条は、以下のように規定しています。
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない(刑法264条)。
器物損壊罪は、刑法261条に規定されているとおり、「他人の物を損壊」した場合に成立する犯罪です。
器物損壊罪における「他人の物」とは、公用文書・私用文書・建造物以外の他人の物を指します。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、物理的損壊を含む物の効用を滅失させる行為をいいます。
刑事事件例において、AさんがVさんの乗用車のフロントガラスなどを叩き割る行為は、器物損壊罪における「他人の物を損壊する」行為に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには器物損壊罪が成立すると考えられます。
【器物損壊事件と示談】
器物損壊罪は、上述の通り、「第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない」(刑法264条)と規定されています。
告訴とは、器物損壊罪を含む犯罪の被害者の方(及びその他一定の者)が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告して、その訴追を求める意思表示をいいます(刑事訴訟法230条)。
器物損壊罪は、この告訴がなければ公訴を提起(刑事裁判へ提訴)することができません。
そこで、刑事弁護士としては、刑事損壊事件の被害者の方と示談交渉をし、告訴を取り消してもらうことができると考えられます。
示談交渉においては、Vさんの乗用車のフロントガラスなどの修理にかかった損害賠償金を支払う被害弁償ができると考えられます。
特に本件器物損壊事件のようなケースでは、被害者の方の情報(氏名や電話番号)が分からない場合が多いです。
そこで、刑事弁護士としては、本件器物損壊事件を捜査する警察官や検察官に対して、弁護士限りで本件器物損壊事件の被害者の方の連絡先を教えてもらえないかと打診することもできると考えられます。
示談締結は、器物損壊事件を起こした場合において寛大な処分を獲得するためには非常に重要な要素となります。
そして、このような示談交渉には刑事事件に関する専門的な知識と豊富な経験が必要であるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊事件において示談交渉を含む刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
三重県亀山市の器物損壊事件で示談を目指す場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
無免許運転幇助事件で否認したい
無免許運転幇助事件で否認したい
無免許運転幇助事件で否認したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
会社員の女性Aさんは、三重県菰野町に住んでおり、交際相手である会社員Bさんと同棲しています。
Aさんは自身の所有する自動車を持っており、普段は自分で運転して買い物に行っていたのですが、その日はたまたま予定が埋まっていたため、Bさんに自動車の鍵を渡すと、運転して買い物に行ってもらうよう頼みました。
Aさんは、Bさんが運転免許を持っていると聞いたことがあったためそのように頼んだのですが、実はBさんは交通違反を重ねた結果免許を失効していました。
Bさんは免許を失効していることをAさんに伝えず、Aさんの頼みに従ってAさんの自動車を運転して買い物に出かけました。
しかし、その道中、三重県四日市西警察署の警察官が交通検問をしており、そこでBさんの無免許運転と、Bさんが運転していたのがAさんの自動車であることが発覚しました。
Aさんは無免許運転の容疑で逮捕され、加えてBさんも無免許運転の幇助の容疑をかけられてしまいました。
困ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、自分は無免許を知らずに頼んだのだと相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転の「幇助」?
無免許運転をした人が処罰されることは当然のことであり、不思議のないことではありますが、無免許運転の幇助をした人にも犯罪が成立して処罰されることには注意が必要です。
幇助とは、手助けをすることで犯罪をすることを容易にすることを言います。
つまり、無免許運転することを容易にすることも犯罪となり、処罰されうるということになるのです。
まず、道路交通法では、無免許運転を禁止しており、以下のような規定があります。
道路交通法第64条第1項
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
そして、無免許運転の幇助については、道路交通法で以下のような規定があります。
道路交通法第64条第2項
何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。
道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2号 第64条(無免許運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第1項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。)
つまり、無免許運転をする可能性のある人に車を提供し、その人が実際に無免許運転をしてしまった場合、車を提供した人は、実際に無免許運転をした人と同じ範囲の重さの処罰を受けることになるのです。
実際に無免許運転をしているわけではないのに実際に無免許運転をしている人と同じだけの刑罰の重さが設定されていることからも、決して軽視してよい犯罪ではないのだということが分かります。
・無免許運転幇助事件で容疑を否認する
今回のAさんは、無免許運転をしたBさんに車を使わせていたことから、車の提供による無免許運転幇助を疑われています。
AさんはBさんと同棲もしていたことから、Bさんが無免許状態であることを知っていたのではないかと疑われているのでしょう。
ですから、Bさんが無免許状態であったことを知らなかったということを、きちんと主張していくことが必要とされるでしょう。
しかし、多くの人は刑事事件の当事者となったことはなく、取調べのプロである警察官や検察官に自分の主張を適切に伝えることが難しいことも少なくありません。
だからこそ、弁護士のフォローを受けながら取調べへ対応していくことが有効となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転幇助事件のご相談もお受けしています。
かけられてしまった容疑を否認したいとお悩みの方、取調べへの対応にお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
暴行・脅迫なしでも強制性交等罪に
暴行・脅迫なしでも強制性交等罪に
暴行・脅迫なしでも強制性交等罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県四日市市に住んでいるAさんは、市内にある商業施設Xにある個室トイレを利用していた小学4年生のVさんに対し、自分の性器を口にくわえさせるなどのわいせつな行為をしました。
その際、AさんはVさんに暴行をはたらいたり脅しつけたりしたわけではなく、個室に入ってきたAさんに驚いたVさんの隙を見てわいせつな行為をしていました。
Vさんは、トイレから出ると一緒に買い物に来ていた両親にAさんにされたことを相談し、Vさんの両親はすぐに三重県四日市南警察署に通報しました。
三重県四日市南警察署の捜査の結果、Aさんは強制性交等罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんが逮捕されたことを知り、三重県の逮捕にも対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制性交等罪とその対象
今回のAさんは、強制性交等罪という犯罪の容疑をかけられています。
強制性交等罪はもともと「強姦罪」として刑法に定められていたものが、平成29年(2017年)の改正によって新設された犯罪です。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文を見ると、強制性交等罪は「性交」・「肛門性交」・「口腔性交」を対象の行為としています。
旧強姦罪では、性器へ性器を挿入する「性交」だけを処罰の対象行為としていましたが、強制性交等罪では、それに加えて肛門への性器の挿入を伴う「肛門性交」と、口腔内への性器の挿入を伴う「口腔性交」を追加しています。
強制性交等罪では、これらをまとめて「性交等」とし、処罰の対象行為としているのです。
ですから、いわゆる「本番」に至らなかったとしても、強制性交等罪が成立する可能性があるということになるのです。
もちろん、これらの「性交等」がただ行われたというだけでは強制性交等罪にはなりません。
強制性交等罪の成立する要件は、この「性交等」が①「13歳以上の者に対し。暴行又は脅迫を用いて」行なわれるか、②「13歳以下の者に対し」行なわれた場合です。
①被害者が13歳以上の場合
強制性交等罪では、被害者の年齢が13歳以上なのか13歳未満なのかによって成立する条件が異なります。
条文によると、被害者が13歳以上の者であった場合、「性交等」が行なわれた際に「暴行又は脅迫」が用いられることで強制性交等罪が成立します。
この「暴行又は脅迫」は、被害者の抵抗を押さえつける程度の強さが必要であるとされています。
強制性交等罪は、被害者の意思を暴行や脅迫によって押さえつけて無理やり性交等をすることが犯罪とされているためです。
例えば、凶器を突きつけて脅して性交等をする、被害者の手足を拘束して性交等をするなどのケースが考えられるでしょう。
②被害者が13歳未満の場合
被害者の年齢が13歳未満の場合、強制性交等罪では「性交等」をしただけで犯罪が成立することになります。
①のケースとは異なり、暴行や脅迫をしていなくとも、ただ「性交等」をしただけで強制性交等罪となるため、たとえ被害者の同意を得て行なった「性交等」であったとしても強制性交等罪となります。
なお、①のケースでも②のケースでも、条文では「13歳以上の『者』」、「13歳未満の『者』」と書かれていることから、被害者の性別については限定がないことが分かります。
この点も、旧強姦罪との異なる部分でしょう(旧強姦罪では、被害者の性別が女性のみに限定されていました。)。
今回の事例を考えてみましょう。
事件の被害者Vさんは小学4年生ですから、「13歳未満の者」です。
つまり、先程の②のケースにあたり、Vさんに「性交等」をしただけで強制性交等罪が成立することになります。
今回のAさんはVさんの口に自分の性器を挿入していることから、「口腔性交」をしています。
②で確認した通り、13歳未満のVさんに「口腔性交」=「性交等」をした時点で、暴行や脅迫がなくとも強制性交等罪が成立するということになるのです。
強制性交等罪は、法定刑も重い重大犯罪です。
示談交渉や釈放を求める活動を並行して行なわなければならないことも多く、当事者だけでは対応できないこともあるでしょう。
だからこそ、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制性交等事件を含む刑事事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。